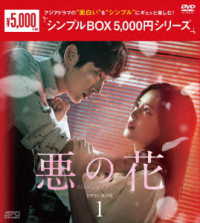目次
序章 成果をあげるには
第1章 成果をあげる能力は修得できる
第2章 汝の時間を知れ
第3章 どのような貢献ができるか
第4章 人の強みを生かす
第5章 最も重要なことに集中せよ
第6章 意思決定とは何か
第7章 成果をあげる意思決定とは
終章 成果をあげる能力を修得せよ
著者等紹介
ドラッカー,ピーター・F.[ドラッカー,ピーターF.][Drucker,Peter F.]
1909‐2005。20世紀から21世紀にかけて経済界に最も影響力のあった経営思想家。東西冷戦の終結や知識社会の到来をいち早く知らせるとともに、「分権化」「目標管理」「民営化」「ベンチマーキング」「コアコンピタンス」など、マネジメントの主な概念と手法を生み発展させたマネジメントの父
上田惇生[ウエダアツオ]
ものつくり大学名誉教授、立命館大学客員教授。1938年生まれ。61年サウスジョージア大学経営学科留学、64年慶應義塾大学経済学部卒。経団連会長秘書、国際経済部次長、広報部長、(財)経済広報センター常務理事、ものつくり大学教授を経て、現職。ドラッカー教授の主要作品のすべてを翻訳、ドラッカー自身から最も親しい友人、日本での分身とされてきた。ドラッカー学会代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
58
ドラッカー自身一番の思い入れのある本ではないかと思います。ドラッカーの三大古典のひとつで、今では比較的企業内部では常識になっていることが語られています。私の何度目かの再読なのですが、6章、7章の意思決定に関するところはいつも参考になります。2015/04/01
なかしー
45
再読。成果≒アウトプットを中心に物事を考える本。 人間とコンピュータの違い:知覚か?論理か?コンピュータは論理演算で、客観的データに基づく処理を行うこれが強みである。対して、人間は外界から様々な情報を「知覚」が出来る、これが強みである。しかし、人間は知覚を優先するあまり客観的データを疎かにしてしまう。コンピュータが得意なことは任して、我々に出来ることに集中する事が大事。2024/12/30
みき
41
経営学の古典的な名著。名だる経営者も座右の書のにあげている方も多いだけあって内容もさることながら言葉にパワーがあり、パワーのある言葉は人の行動を変えることが出来る。そんな名著。しかしこの本は厳密に言うと経営に関する本ではなく成果を出すための具体的な方法について書かれている。時間の使い方や仕事に対しての取り組み方などは今となっては陳腐化しているものもあるが、逆説的に言えば何十年も前に書かれている原則がまだほとんどの人が出来ていないことを表している。仕事で成果を出したい人やラクして成果を出したい人は必読の1冊
アベシ
33
エグゼクティブの仕事、それは知識労働であり量やコストによって規定されるものではなく、ただ成果によって規定されるものである。この成果を上げるためには8つの習慣と5つの能力が必要。ドラッカーが言っていることは引用する例示がいかに古くなろうとも普遍的である。曰く、あらゆるプロセスにおいて成果の限界を規定するものは、最も欠乏した資源である。時間こそ真に普遍的な制約条件である。成果を上げるものは時間からスタートする。今更、耳が痛い話ではある。5つの能力のうち3番目の強みを基盤することくらいしかできることはない。2023/11/03
十川×三(とがわばつぞう)
27
1966年刊行の古典ビジネス名著。読むと、経営者への本ではなく「普通の働く人」への本だと分かる。無駄のない濃密な内容。社会人必読書。付箋だらけ。繰り返し読む。▼書籍「エッセンシャル思考」「ストレングス・ファインダー」などは、本書の各章を1冊に展開したのでは?と感じた。ビジネス書の源泉ともいえる書。2020/04/29