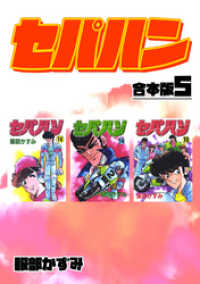内容説明
日本は、資本主義経済と議会制民主主義の歴史においては後発国であるが、それゆえに西欧諸国の過去一世紀の経験に学び、彼らと同じ轍を踏むことを避けることができる。今後、日本が経済再生を果たし、市場の繁栄と健全な福祉制度を両立させ、激しく変化する世界の中で自らの意見や立場を主張していくということはけっして容易ではないだろう。しかしそれは「可能である」と私たちは考える。本書は、こうした目標を実現するために今後日本がとるべき方向性と方法論を提示するものである。
目次
第1章 二一世紀の新たな社会モデル(産業構造の転換と社会変動―低炭素産業社会の到来;市場経済・政府・市民社会のバランス ほか)
第2章 グローバル・ガバナンスの構築に向かって(グローバル化はもはや「事実」である;一次元的な世界の形成 ほか)
第3章 「第三の道」と日本の選択(日本の現状と「第三の道」議論;「第三の道」の基本理念 ほか)
第4章 「欧州社会モデル」からの教訓(「欧州社会モデル」とは;ヨーロッパに学ぶべき一〇の教訓 ほか)
第5章 新社会への価値観変革―環境とポジティブ・ウェルフェア(低炭素産業社会への価値観変革;環境とライフスタイル変革)
著者等紹介
ギデンズ,アンソニー[ギデンズ,アンソニー][Giddens,Anthony]
ハル大学卒業。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)より社会学修士号、ケンブリッジ大学より社会学博士号(Ph.D.)を取得。ケンブリッジ大学教授(1985~1997年)、LSEディレクター(最高責任者、1997~2003年)を経て、現在、英国貴族院議員、LSE名誉教授。現代社会学の権威であり、トニー・ブレア政権の「第三の道」改革を理論的に主導したことで世界的に知られる
渡辺聰子[ワタナベサトコ]
東京大学社会学科卒業。米国ボストン大学大学院博士課程を修了。ボストン大学より社会学修士号、社会学博士号(Ph.D.)を取得。国際大学助教授を経て、1997年より上智大学総合人間科学部社会学科教授。英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス客員教授、(独)国立環境研究所客員研究員、経済産業省産業構造審議会委員、文部科学省科学技術学術審議会委員などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
taming_sfc
メルセ・ひすい
かんちゃん
脳疣沼
ふぁいと