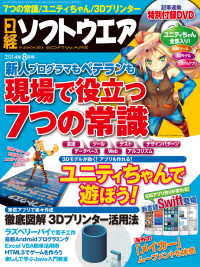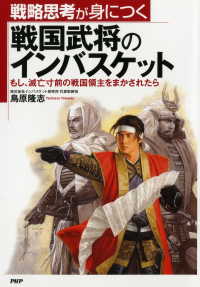内容説明
IQの違いはどこから生まれるのか?人間の知能を決めるのは遺伝か環境かをめぐって、アメリカを代表する社会心理学者が明らかにした驚愕の事実!知能の本質に迫り、知能を高めるための具体的な方法を示す。
目次
第1章 知能の種類は1つではない
第2章 遺伝子はどれほど重要なのか
第3章 学校は人を賢くする
第4章 学校をさらによくするための方法
第5章 貧富の差は知能に大きな影響を及ぼす
第6章 黒人と白人のIQ
第7章 知能の差は縮められるのか
第8章 アジア人のほうが賢いか
第9章 ユダヤ人の教育の秘密
第10章 あなたの子供、そしてあなた自身の知能を高める
エピローグ 知能と学力についてわかっていること
著者等紹介
ニスベット,リチャード・E.[ニスベット,リチャードE.][Nisbett,Richard E.]
ミシガン大学心理学教授。アメリカ心理学会科学功労賞、アメリカ心理学協会ウィリアム・ジェームズ賞、グッゲンハイム・フェローシップ受賞。2002年、同世代の社会心理学者として初めて全米科学アカデミー会員に選ばれる
水谷淳[ミズタニジュン]
翻訳家。東京大学理学部卒。博士(理学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
シュラフ
27
人の知能の高さを決めるのは遺伝なのか、それとも環境なのか。実証の難しい問題ではあるが、きわめて重要な問題である。環境決定論の立場にたつのであれば、子供の教育は放任主義でよいが、環境決定論の立場にたつのであれば国が支援すべきである。著者の立場は環境決定論。東アジアの国々やユダヤ人の知能の高さは、その伝統文化からきていることを根拠として挙げる。その立場から、所得格差の穴埋めとして教育費補助などの社会政策の充実、環境改善による知能向上が可能なことの認知、などを訴える。現在日本の子供支援議論の考察の一助になる。2017/08/20
ステビア
20
完全な遺伝決定論も完全な環境決定論も同様に愚かだという印象/この本は遺伝論者に反駁したいがために、あるいは環境の影響を多く見せたいがために粗雑な(少なくともunpersuasiveな)議論をしているように思える/イデオロギーを離れた冷静な議論や記述はとても難しい。だからこそ価値がある/知能に関して言えば、栄養不良や虐待、貧困などの環境が悪い影響を与えることは間違いないが、遺伝性を全く否定することも同様に難しいだろう2021/07/06
りょうみや
13
最近は「言ってはいけない残酷すぎる真実」がベストセラーになったように知能は環境派よりも遺伝派の方が声が大きい。しかし、ほぼ遺伝で決まり教育は結局は知能を底上げしないという見解は私にはかなり違和感があった。本書の結論は遺伝の影響は認めつつも環境の影響は相当大きいというものである。これまでの遺伝派の実験・調査の不備な部分を鋭く指摘している。人種間、特に白人と黒人で知能に遺伝的に差はないと言っているのは大胆。教育本としても得られるものは多い。2017/09/15
つっきーよ
2
頭の良さは遺伝子でほとんど決まると言われていたが、実は環境要因も大きい。例えば、白人と比べて黒人はIQが低い。人種によって頭の良さが違う、つまり、遺伝すると考えられていた。けれど、そうではなく、黒人のほうが白人と比べて環境的に貧しく、貧しいからこそ十分な教育受けられない。実は環境要因が大きく関わっていた。また、アジア人のほうが数学ができるというデータもあるが、アジア人のほうが数学は努力すればできるようになる。という考え方を持っているため、白人以上に努力をする傾向があった。2022/01/16
novutama
2
職業的興味と個人的興味双方から手にした。残念な邦題を大きく裏切る良書。「遺伝か環境か」という二者択一の罠に私達はすぐに引っかかる。科学的手法をまとった双生児研究の中に潜む誤謬も鮮やかに指摘する。知能の遺伝性が実証以上の市民権を得て独り歩きし、環境要因の軽視が社会的な損失に繋がっていく。経済的かつ精神的に貧しい養育環境が知能の発達を阻害するのは明らかであるのに、遺伝要因を重視し続けるのは不作為による罪に繋がる。故に著者は「政治的に正しい信念」として知能における環境要因の重要性を殊更に説いているのだ。2013/12/06