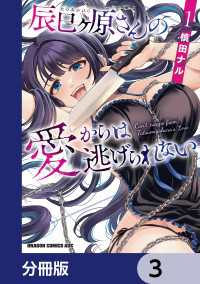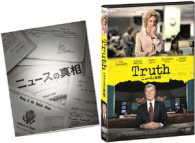内容説明
『家と世界』は、作者の中期の作品で、初・中期の抒情性に充ちた古典的・文語的世界から、中・後期の現代的・口語的世界へと展開するタゴールの作品史の転回点となった小説である。物語は、今世紀初頭、スワデシ運動の嵐に揺れるベンガル地方の一農村の地主家を舞台に、その家の主人ニキレシュとその妻ビモラ、そしてスワデシ運動の指導者ションディプ―この三者の交互の独白によって進行する。小説の中軸は、この三者の三角関係の葛藤であり、特にビモラとションディプの間の「不倫の恋」の当時としてはきわめて生々しい心理描写である。