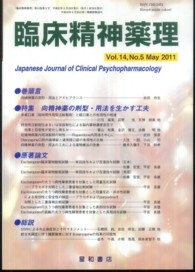出版社内容情報
職員を採用しても短期で辞めてしまい困っている税理士事務所に向けて、働き続けたいと思える事務所運営について解説する。職員を採用しても短期で辞めてしまい困っている税理士事務所では、どうすれば優秀な人材を集め、活き活きと働いてもらえるのか。税理士事務所ならではの「楽しさ」「やりがい」からプロとしての誇りを育み、働き続けたいと思える事務所運営について解説する。
○所長税理士が、「楽しさ」「やりがい」「プロとしての誇り」を職員に伝える取組みについて事例を紹介
○働き続けたいと思える事務所の組織・体制づくりのポイントを解説
第1章 “職員”は、なぜいなくなる?
「税理士法人制度の創設」と「税理士広告の自由化」が変えたもの
人材採用は今「売り手市場」?人手不足と残業過多のスパイラル?
若い税理士試験5科目合格者は、まさに“希少価値”
一般企業でも、有資格者を積極採用しはじめた
少子高齢化で労働人口自体が減少する
職員が辞めていくスパイラル
無資格者が転職を考えるタイミングは“税理士試験合格”
資格取得をあきらめたら、好条件の地域の有力な一般企業へ
有資格者が転職に求める条件とは
一般企業へ転職する有資格者が増えている
それでも働き続けるのには“特別な理由”がある
第2章 “集まる”?「共感」と「見える化」?
離職率10%はやむを得ないことではない
トップ自らが採用プロジェクトの舵を取る
採用担当には仲間から信頼されている職員を
「共感」をキーワードに「人材のミスマッチ」をなくす
ここ20年で人材の採用方法は大きく変わった
人材採用方法の種類と特性を理解する
ウォンテッドリーに見る日本型ビジネスSNSの可能性
ダイレクトリクルーティング?インディードが起こす採用改革
これからの採用戦略は「定着率」がカギを握る
事務所を外から「見える」ようにする
応募の“入り口”を見直す
採用決定までのプロセスと中身を見直す
第3章 “育つ”?「働きがい」と「多様な働き方」?
人々の「働き方」に異変が起きている
「働きがい」を考えるキーワードは「ビジョン」「成長」「仲間」
トップ自らが「ビジョン」を実践する
「成長」を感じられる企業風土と人事評価制度をつくる
「仲間」「居心地」が働く意欲を生む
なぜ「多様な働き方」が求められるのか?
「イクボス」的マネージメントが環境を変える
長時間労働は改善できるか?
まず管理職の労働時間から見直そう
「時間」を人事評価の基準に加える
残業の“中身”を管理する
固定残業代は長時間労働に繋がる
“サービス早朝出勤”が組織の生産性を下げる
「定時以上が当たり前」という“風土”を変える
働く時間と場所に柔軟性を持たせる
フレックスタイムにまつわる勘違い
税理士事務所における裁量労働制のルールと運用
変形労働時間制の活用で週休3日という働き方
「多様な働き方」は経営者も職員も幸せにする
第4章 “元気になる”?「相互信頼」と「社会的価値」?
仕事を“任せる”姿勢が職員を成長させる
「人材ポリシー」を考える
やりたい仕事にチャレンジできる環境と風土をつくる
“やるだけ”研修を見直す
職員の「家族」を大切にする
「育休制度」を組織のパワーアップにつなげる発想
未経験者を積極採用する
「出戻り」も「副業」も“経験”である
働きやすい仕事場をつくる
健康意識の高い事務所は収益性が高い
働く場所の“縛り”をなくす
テレワーク導入のルール作り
働くことも遊ぶことも“自分の意志”で決める
休むことも休ませることも「仕事のうち」
どうしても休みが取れない場合の代替措置
急用には「時間単位」の有給休暇を
障害者雇用を考える
税理士事務所が障害者を受け入れる社会的意味
無自覚なパワハラ体質が“いい人材”を遠ざける
パワハラを防ぐ仕組みをつくる
“風通し”のいいところには人が定着する
一般社団法人 租税調査研究会[イッパンシャダンホウジン ソゼイチョウサケンキュウカイ]
著・文・その他
内容説明
職員から愛される税理士事務所とは?“人材”計画に悩む所長税理士に必携の書。
目次
第1章 “職員”は、なぜいなくなる?(「税理士法人制度の創設」と「税理士広告の自由化」が変えたもの;人材採用は今「売り手市場」―人手不足と残業過多のスパイラル ほか)
第2章 “集まる”―「共感」と「みえる化」(離職率一〇%はやむを得ないことではない;トップ自らが採用プロジェクトの舵をとる ほか)
第3章 “育つ”―「働きがい」と「多様な働き方」(人々の「働き方」に異変が起きている;「働きがい」を考えるキーワードは「ビジョン」「成長」「仲間」 ほか)
第4章 “元気になる”―「相互信頼」と「社会的価値」(仕事を“任せる”姿勢が職員を元気にする;「人材ポリシー」を考える ほか)