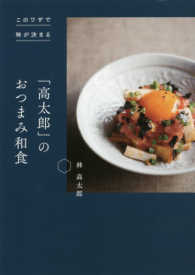内容説明
「若鶏冠木」の重ね、「雪の下」の重ね→由来は…!豊富な写真資料と文献で「平安人の見ていた色彩」がそのままわかる!全370項目以上、日本の伝統色や装束の色目を掲載。『有職装束大全』の著者による、充実の色図鑑。
目次
第1章 有職の色―染色(深紅;中紅 ほか)
第2章 表裏の重ね色目(梅・白梅;梅重 ほか)
第3章 衣のかさね色目(『満佐須計装束抄』;『女官餝抄』 ほか)
第4章 織色(薄色;半色 ほか)
第5章 〓の色(紫〓;棟〓 ほか)
第6章 位当色―当色
著者等紹介
八條忠基[ハチジョウタダモト]
綺陽装束研究所主宰。全国の大学・図書館・神社等で講演多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
255
著者の八條忠基氏は、有職故実の研究家。綺陽装束研究所を主宰する。『延喜式』(927年完成)に見る五色(青・黃・赤・白・黒)は陰陽道に基づく基本色である。そこからはバリエーションということになるが、紅だけでも、「深紅」(こきくれない)、「中紅」(なかくれない)、「退紅」(たいこう)とあり、赤は他にも「赤白橡」(あかしらつるばみ)、「掻練」(かいねり)、「火色」(ひいろ)、「深緋」(ふかひ)「浅緋」(あさあけ)、「朱祓」(しゅふつ)、「深蘇芳」(こきすおう)以下に続いていく。よくこれだけ微細な色の違いを⇒2025/03/30
ふう
67
四季のある国ならではの、自然の移り変わりとともに少しずつ変化していく草花や樹木の色を取り入れた染色が紹介されています。色も繊細で美しいけど、表す言葉も「朽葉」「赤朽葉」「黄朽葉」など味わい深いものがたくさん。皇位継承の儀式の折、天皇だけに許された色と紹介された黄櫨染をはじめ、制度や位によって身につけることが許されていた色も紹介されています。衣服に取り入れるのは難しいけど、暮らしの中に取り入れたくなる色もありました。ただ、花や緑が溢れている今の季節は、窓から見える自然の色に勝るもの無し、でしょうか。2024/04/23
彩菜
37
オールカラーの美しい本で、平安以来の色彩の雅と基礎知識を丁寧に教えてくれます。例えば同じ「あか」でも紅は紅花染めで私的なお洒落、緋色は茜染色で公的に用いられたのだそう。またそれぞれの色の染料や重ね色目のモデルとなった植物や動物の写真が充実しているのも楽しいです。青、浅黄、白+蘇芳=白梅、薄色+青=楝、黄+青=女郎花…色彩と写真から言葉が記号となりイメージを喚起する星座となるように、色が記号となり様々にイメージを結んでゆくのが良く解ります。自然の彩りを愛しそれを詩のように生活に取り入れていたなんて素敵だなー2023/11/20
たまきら
31
フルカラー、うっとりする美しい色の図鑑です。天然の染料や色の説明部分を楽しく読みましたが、両方が微妙に混ざっているため、水溶性のツユクサ色素でこんな色が本当に出るんだろうか?とかちょっと早とちり。材料に興味がある人間と、色が持っていた肩書という側面に興味がある人、どちらも満足させるのは大変よね。後半の色の組み合わせはあちこちで最近見てきましたが、印刷が美しく説明も私好みで、今まで読んだ類似の本の中で一番勉強になりました。2024/03/30
ひめありす@灯れ松明の火
24
夏虫の襲。かわせみのあお。早蕨。菖蒲の勝負…小栗色。こき栗色…移ろいぎく…虫青。松の雪。唐紙。おりの色。だんのいろ。裏山吹。蝉の羽。2021/04/07
-

- DVD
- 悲惨物語(ヘア無修正版)