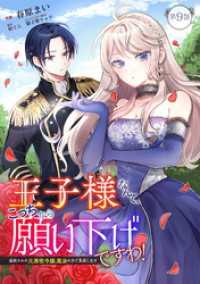出版社内容情報
東京は一日にして成らず。大火や文明開化などの大きな転換点を捉えつつ、東京の都市形成史の「流れ」を一冊で追います。〈江戸は、どのようにして「東京」になっていったのか〉〈これ一冊で都市・東京の歴史変遷のポイントが押さえられる!〉
台地と低地、海と湿地と川がおりなすダイナミックな地形を活かして作られた「坂と水の町」東京。徳川幕府による計画、大火や地震などの災害、文明開化、戦争、高度成長など、現在の発展の前には、都市が劇的に変革する数多の大きな起点が存在していました。それらのプロセスや出来事の重要性を、古地図・史料・風景写真、そして現代のまちを歩いて得た知見などを交えつつ、「ブラタモリ」にも出演した都市形成史の専門家がわかりやすく解説します。オリンピックを控える今、江戸の町と現在の町の利点・難点を比較し、未来の町づくりを考えるきっかけとなる一冊です。
岡本哲志[オカモトサトシ]
都市形成史家
内容説明
江戸から昭和、平成の時代とともに、山の手・下町・埋め立て地として巧みに地形を利用しながら変化を遂げたプロセスを読み解き、江戸東京の成熟した都市空間を古地図や写真図版を配し、ビジュアル的にも復元する。「ブラタモリ」7回出演のエキスパートが送る歴史散歩解説。
目次
プロローグ 高低差のある地形にできた江戸
第1章 江戸に描いた家康の都市未来像
第2章 大火を呼ぶ江戸の地霊
第3章 成熟した江戸文化の開花
第4章 幕末の動乱とその後の近代化(明治期)
第5章 サラリーマンの誕生と郊外生活(大正期)
第6章 昭和モダンと「東京行進曲」
第7章 焼け跡から高度成長の時代へ
第8章 超高層の時代をむかえた現代東京
著者等紹介
岡本哲志[オカモトサトシ]
1952年、東京都生まれ。法政大学工学部建築科卒業、岡本哲志都市建築研究所主宰。専攻は都市形成史。元法政大学教授、都市形成史家、博士(工学)。日本各地の都市と水辺空間の調査・研究に長年携わる。銀座、丸の内、日本橋など、東京の都市形成史をさまざまな角度から40年以上調査、研究を続けている。2009~2012年にかけてNHK総合テレビ「ブラタモリ」に案内人として計7回出演して人気を博した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yutaro13
ころこ
鉄之助
Wataru Hoshii
HALI_HALI