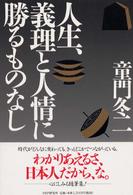出版社内容情報
なぜ、茶室に掛物をかけるようになったのか? 素朴な疑問を出発点にして、茶掛けの基本から茶会の実際まで話をひろげていきます。〈なぜ、茶室に掛物をかけるようになったのか?〉
〈新進気鋭の筆者による?新しい? 茶道教養講座」全16巻。第六回配本〉
なぜ、茶室に掛物をかけるようになったのか? 素朴な疑問を出発点にして、茶室の掛物(茶掛け)の歴史、種類など、基本的な事項を概観するとともに、「茶会と掛物をめぐる物語」といった章を設けて、道具との取り合わせをからめた茶掛けの話をお届けします。
宮武慶之[ミヤタケヨシユキ]
著・文・その他
内容説明
茶を点てるのに茶碗や棗が必要なのは当然だが、ではなぜ、掛物が必要なのか?その理由を考えながら、中国宋時代の名画、禅僧の墨蹟、和歌懐紙、消息などの筆跡から、近代の数奇者や画家・書家の筆跡までを鑑賞していきます。
目次
第1章 床の間と掛物
第2章 掛物を知る
第3章 掛物の表具と付属品
第4章 茶の湯の掛物の歴史
第5章 名物とその流通
第6章 茶人と掛物をめぐる物語
第7章 近代の掛物
第8章 掛物にみる茶の心
著者等紹介
宮武慶之[ミヤタケヨシユキ]
同志社大学研究開発推進機構特任助手。1982年、三重県生。明治大学商学部グローバル・ビジネスコース卒業後、企業勤務を経て、同志社大学大学院文化情報学研究科博士後期課程修了。文化情報学博士。専門は大燈国師墨蹟研究、溝口家旧蔵品および茶の湯文化研究、吉村観阿研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
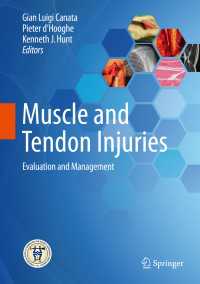
- 洋書電子書籍
- Muscle and Tendon I…