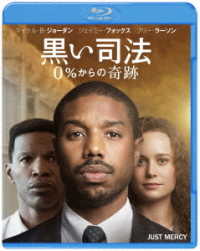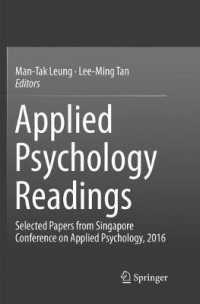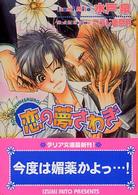出版社内容情報
近現代の作家の感性を通して京都の伝統の味、真の風味を探る。
1,200年以上の歴史の中で育まれ、今日、観光客・美食家にもてはやされる京料理ですが、夏目漱石・谷崎潤一郎・林芙美子など明治から平成にかけて京都に訪れた文学者たちは、京都で何を食べ、何を感じていたのでしょうか。近・現代を中心とした約50名の小説家・文化人たちの作品にみられる記述・表現を通して、京都の食の今昔や現代との相違を探ります。そして書き手の個性や時代相を通して、現代人の美食ブームとは一味違う味覚、または不変な美味の世界を照らし出します。
【著者紹介】
ノンフィクション作家
内容説明
一、二〇〇年以上の歴史の中で育まれ、今日、観光客・美食家にもてはやされる京都の料理だが、夏目漱石・谷崎潤一郎・林芙美子・池波正太郎をはじめ、明治から平成にかけて京都に訪れた文学者たちは、京都で何を食べ、何を感じたのだろうか。近・現代を中心とした小説家・文化人たちの作品にみられる京都の食べ物にまつわるできごとやその記述・表現を通して、現在も継承される味、失われた風味など京都の食の今昔や現代との相違を探る。書き手の感性や時代相を通して描き出される、現代人の美食ブームとは一味違った、作家たちの京都の味覚の世界「食景」を照らし出す。
目次
第1章 作家が描いた「京名物」春夏秋冬(筍―春の美菜;鱧―谷崎は執心、漱石は閉口;川魚料理―鰉・鮴・鷺知らずの魚影薄く ほか)
第2章 老舗の味と作家たち(瓢亭―作家たちが浸った侘びの店構え;二軒茶屋中村楼―豆腐の曲切りの音は遠く;平八茶屋―若狭街道と高野川を地の利とした鄙の時間 ほか)
第3章 近代作家 それぞれの食景(夏目漱石と善哉の赤提灯;河上肇と進々堂のパン;川端康成『たまゆら』の食景―上賀茂の焼餅があぶり出すもの ほか)
著者等紹介
菊池昌治[キクチマサハル]
1947年、山形県南陽市生まれ。立命館大学文学部日本文学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
アメヲトコ
とす
イナサ
-
![立ち食いそば大図鑑[首都圏編]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0848312.jpg)
- 電子書籍
- 立ち食いそば大図鑑[首都圏編]
-

- 電子書籍
- 小四教育技術 2017年 12月号