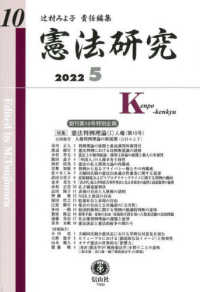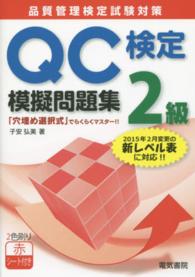内容説明
現代の日本人には仏教思想が浸透していて、人は死ぬと「ホトケ」になると思っている。しかし、日本には、古来、人を神に祀り上げる習俗があった。その思想とメカニズムを解明する。「崇拝」「怨霊」「権力」「民衆」をキーワードに、藤原鎌足、源満仲、安倍晴明などを取り上げ、日本人の「神」観念を考える。
目次
第1章 崇拝(藤原鎌足―談山神社;源満仲―多田神社 ほか)
第2章 怨霊(井上内親王・早良親王―上御霊神社;菅原道真―北野天満宮 ほか)
第3章 権力(楠木正成―湊川神社;豊臣秀吉―豊国神社 ほか)
第4章 民衆(李参平―陶山神社;お竹―羽黒山お竹大日堂 ほか)
著者等紹介
小松和彦[コマツカズヒコ]
1947年、東京都生まれ。1976年、東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学。信州大学助教授・大阪大学文学部教授を経て、現在、国際日本文化研究センター教授。文化人類学者にして民俗学者。主な研究は、日本民俗文化の構造と比較
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
にゃも
7
崇拝・怨霊・権力・民衆の4つの章に分け、16人の『神になった人々』が取り上げられている。深く掘り下げられて書かれてはいないが、神として祀られるようになった経緯が興味深い。記憶をとどめておくための記念館的な意味も含んでいるという言葉が印象に残った。2024/04/16
Humbaba
6
日本人は昔から,死者をホトケとして敬っていた.特に,力のある人物が亡くなったときには,それを神として祀ることで自分たちにさらなる繁栄を求めた.その心は今も失われておらず,神を作り出している.2010/07/10
遊未
5
崇拝ー藤原鎌足、安倍晴明等。怨霊ー井上内親王、早良親王、佐倉惣五郎、平将門。権力ー楠正成、豊臣秀吉、徳川家康。しかし、楠正成については当人が権力者ではなく権力者が利用。徳川家康は無論権力者だが、埋葬の希望は久能山だった訳で、徳川家のためと吉田神道の力が削がれたということでしょうかその他のケースについては何故神にされねばならなかったをもう少し知りたいところ。教科書で明治の「神仏分離」についてはほとんど言葉のみですが、招いた混乱は大きかったことがわかります。2015/03/02
挫躯魔
3
いやぁ面白かった、偉人さんが祀られたり、有名な人が祀られたりしたのを書いてるんだろうなぁと思っていたけれど、普通の人達も神様として祀られてたんですね。 佐倉惣五郎さんの祟が残ってたら今の政治家たち何人くらい生き残ってるかな?(笑) 読みたい本が増えました。2014/07/17
戦狐
1
タイトルどおり平将門、菅原道真、増田敬一郎などの神として祀られるようになった人たちを紹介されています。 神社の周辺事情、祀られている人神の生前の歴史、祀られるようになった経緯などが分かりやすく書かれています。民俗学好きな人だけでなく、歴史好きな人にも勧めたい一冊です2014/08/19


![Fate/stay night[Unlimited Blade Works] 7 7](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)