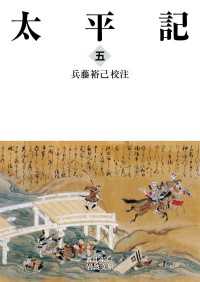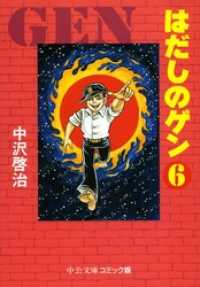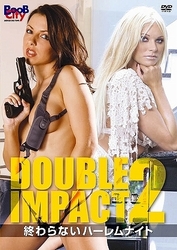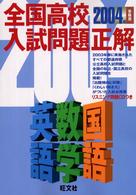出版社内容情報
探究的な〈問い〉のもと、学習者に相互作用をもたらす「読みの交流」。理論を整理しつつ、文学教材を用いた授業事例を分析する。
国語科学習において、文学教材の読みを成立させるには、探究的な〈問い〉をもとにした「読みの交流」が有効である。どうすればよい〈問い〉を作ることができ、交流を活性化できるのか。学習を支える理論を整理・検証しつつ、「白いぼうし」「少年」などでの授業事例を丁寧に分析。ワークシートも付し、教員の実践や研究に役立つ。
はじめに
凡例
第1章 読みの交流の枠組みと読みの交流の成立
第2章 質的三層分析
第3章 語りに着目した教材分析
第4章 読みの交流を成立させる学習課題の条件
第5章 読みの交流のための学習課題の事例
第6章 読みの交流の授業の実際
第7章 読みの時間が読みの交流に与える影響
資料編 ワークシート
おわりに
【著者紹介】
松本 修
玉川大学教職大学院教授。専門は国語科教育、特に文学の教材研究と学習デザイン。1959年、栃木県生まれ。筑波大学第二学群人類学類卒業、宇都宮大学大学院修士課程修了。教鞭をとるかたわら、実践研究団体「Groupe Bricolage」を設立、研究活動を続ける。1995年に上越教育大学助教授に転じ、准教授、教授を経て、2013年から現職。著書に『文学の読みと交流のナラトロジー』(東洋館出版社)がある。
目次
第1章 読みの交流の枠組みと読みの交流の成立
第2章 質的三層分析
第3章 語りに着目した教材分析
第4章 読みの交流を成立させる学習課題の条件
第5章 読みの交流のための学習課題の事例
第6章 読みの交流の授業の実際
第7章 読みの時間が読みの交流に与える影響