内容説明
第一線で活躍中の演劇人たちが熱く語る、「演劇のつくり方」
目次
1 公演の企画
2 脚本・演出の決定
3 公演の宣伝・チケット販売
4 演出計画の実現
5 稽古開始
6 小屋入りから初日へ
著者等紹介
おーちようこ[オーチヨウコ]
フリーライター。10代より趣味の同人誌を作り、広告代理店を経て出版業界へ。20代で演劇と出会い、魅せられる。以後、舞台、本格ミステリ、特撮、お笑いなど心惹かれるまま本の企画・制作を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
123
芝居の題目と出演俳優、脚本家に演出家が表の顔ならば、公演の企画宣伝にチケット販売、舞台美術や照明、音響からメイクなどの裏方は基礎を支える役どころ。どちらが欠けてもうまくいかず、一致協力して初めて素晴らしい舞台が完成する。普段は光の当たらないプロたちのインタビューからは、理想の芝居を創り上げたいという情熱が伝わる。早乙女太一の「舞台に立つとは未来を信じていかに準備ができるかが大切」との言葉は、あらゆる創造的な仕事に携わる人に共通する。優れた共同作業のノウハウを教えてくれる、ある意味ビジネス本としても読める。2025/05/19
kane_katu
8
★★★☆☆芝居を観るのが好きなので、公演がどうやって出来上がっているのかには興味があった。分かりやすく説明してあるし、演出家、脚本家、制作、舞台監督など、各パートを担う実際の人たちへのインタビューも豊富なので大分理解が深まった。今度芝居を観に行ったら、この本を思い出しながら観てみたい。2025/05/13
真琴
5
「一本の演劇作品を上演するために、どんな人々がどういう形で関わっているのか?」芝居好きで、高校演劇に身を捧げた者にとって魅力あふれる一冊。裏方の仕事の幅広を知れ、これまでとは違った視点からも舞台が観れそうです。(推しの次の舞台はいつなのだろう?)2025/03/24
Megumi Hirayama
4
とても丁寧に、この世界の専門家にインタビューされていて読みやすいし、著者が素人目線で聞きたいことを聞いてくれてる感があって満足。作家演出家やプロデューサー等の表に出る人よりも、いわゆる裏方、制作・衣裳・美術・大道具・音響・照明・劇場支配人まで。なぜこの世界に?が面白い。バブル期の興行界隈の話も知れて。個人的に昔を思い出して熱くなる。図書館本だったが、買おうかな。2025/05/10
まちこ
3
舞台が幕を開けるまでの全ての仕事を、実際やってる人達にインタビューして構成した本。最初に鴻上尚史。企画→プロデューサー・座長/脚本→脚本家/演出→演出家、舞台美術家、舞台監督、大道具、舞台衣装家、ヘアメイク/宣伝→制作/稽古→俳優、舞台照明家、舞台音響家/本番→劇場支配人 の各氏に聞いてて面白い。照明と音響が稽古のカテゴリに入ってて納得した、確かにこの2つは稽古でしか創っていけない。舞台監督のあまりの仕事の多さにも驚いた。役者の動きの段取りや安全管理、舞台と大道具の寸法とりに搬入スケジュールまで。大変。2025/10/23
-
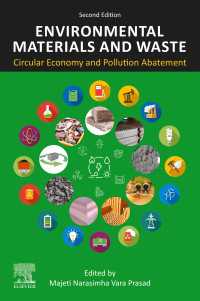
- 洋書電子書籍
- Environmental Mater…








