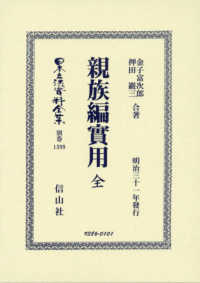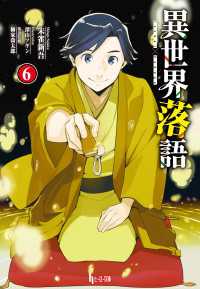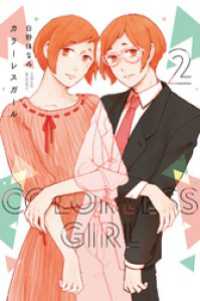出版社内容情報
中国古典(漢文)には実はいろいろな動物が登場します。漢字が多い、おじさんの説教が多い、と難しい印象を抱きがちな漢文ですが、動物たちの活躍ぶりや、人間と動物の付き合い方を知ると、作品に親しみがわいてくるかもしれません。
【目次】
内容説明
いきものを通して漢詩文を読む、漢文世界のガイドブック。
目次
第一章 狐
第二章 虎
第三章 猫
第四章 犬
第五章 鳥
第六章 魚介
第七章 伝説のいきもの
第八章 その他
付録
著者等紹介
高芝麻子[タカシバアサコ]
1977年(巳年)、神奈川県生まれ。東京大学文学部卒業、同大学人文社会系研究科博士課程単位取得退学。文学博士。横浜国立大学教育学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
111
面白かった。虎になる話もいろいろ。人食い虎から人間に戻っても良心の呵責なし、というのが何なんだか 2025/10/20
さとうしん
19
故事成語から志怪・伝奇小説、そして漢詩の中に登場する動物たちの姿を追う。物の拍子で虎に化けたら人間に戻るのも簡単、それで人間を食べても悪びれしない男の話や(李徴……)、中国の古典では化け猫の話は少なく、犬のように不条理な祟り方をすることもないという話、町が洪水で沈んで自分の姿が魚に変わっても気づかずに仕事を続ける役人たち。漢文から見出される動物観、人間観が面白い。2025/07/11
かふ
17
中国の諺に出てくる動物を中心に日本作家が 描いた話のもとネタなどをさぐる本。神話的な動物が多いのかと思ったがそうでもなく狐や猫、犬、鶏などの生き物が語られる。虎は当時は中国に広く分布していたが絶滅危惧種へ。ホトトギスは夏の鳥ではなく、一年中いたがむしろ病をイメージさせることから盛夏は少ないという。そのへんの差異はどうしてなのか気になった(ホトトギスを不如帰と書くのは中国から)。白居易の詩も春の終わりを告げるのに、日本の文化の独自性を言いたかったのか?中国の動物は神話的に語られるようだ。2025/10/15
紫草
13
実は漢文にはあまり興味はなかったんですが、SNSでかわいいねこちゃんのお話をつぶやいていらっしゃるごま先生の本!ということで読みました。先生の動物と人間を見る目があたたかくて、読んでいて心地よい。「これくらい知ってる前提」みたいなのが一切なくて、丁寧に解説してくださっているので何も知らない私も楽しめました。猫は化け猫とかちょっと妖怪っぽい話を今でも聞くけれど、漢文世界では、犬が案外怪しくて、飼い主に忠実でかわいくて人の役に立つという印象と違う姿にちょっとびっくり。あとなんでみんな虎になっちゃうの?2025/07/24
竜王五代の人
12
ファンタジーとリアルの両方に目を配って、中国の文芸では各種の動物(幽霊・竜含む)がどんなものだと捉えられているかのエッセイ集。引用が豊富で読んでいて楽しい。人に化けるのは、狐か竜。虎はむしろ人が化してしまう方。猫は怪異に関わらないものと見られていたなど。サルはマカクとテナガザル(声がもの悲しい方)の2種がいた、というのは漢詩を味わうにあたって注意すべきところだ。2025/08/19