目次
序章 軍歌と恋歌
第1章 新体詩の登場
第2章 「抜刀隊」―新体詩としての軍歌
第3章 志の文学―漢詩の伝統
第4章 共感と追随―新体詩の増殖
第5章 古典派の反撃
第6章 西洋派の一撃
第7章 国民的詩人―民衆歌と叙事詩
第8章 近代詩の成立
第9章 忘れられた実験―自由詩と朗読
著者等紹介
尼ヶ崎彬[アマガサキアキラ]
1947年愛媛県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(美学芸術学専攻)。東京大学助手、学習院女子短期大学助教授・同教授を経て、学習院女子大学教授。美学、舞踊学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
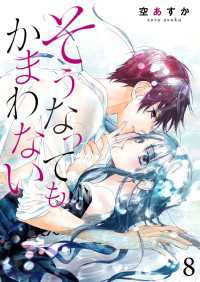
- 電子書籍
- そうなってもかまわない 8巻 Colo…



