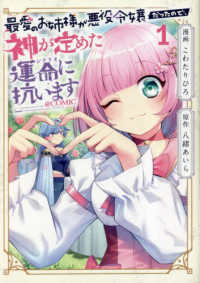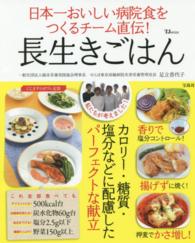出版社内容情報
日本の古代的特質が、その後の歴史の中で、見え隠れしながらも脈々と流れ続けていることを明らかにする。古代文学研究者必読の一冊。
内容説明
古代は、歴史の地底に流れ続け、時として、地表に現出する。古代の生活と思惟をたどることによって知る、日本文学史への指針。
目次
清少納言と「をこの者」
小町像を保持した人々
古代丹波(たには)の研究―宮廷信仰と地方信仰と
天人女房譚の示唆するもの
古今集の成立と歌枕
阿漕が浦の文学
大嘗祭と神楽
七五調の根源
信州遠山の木地屋遺跡―四十二年ぶりの採集報告
著者等紹介
西村亨[ニシムラトオル]
1926年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。国文学を専攻。在学中から折口信夫に師事し、古代学の継承と王朝の和歌・物語の研究に努める。慶應義塾中等部教諭を経て、1970年大学文学部に移籍。74年教授。80年文学博士の学位を取得。89年退職して、名誉教授となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
興味深い指摘。「調査をしている間に分かってきたことは大正九年の折口先生の三信遠国境地帯の旅のコースがもう少し北に寄っていたならば、その旅の成果が違ったものになっていただろうということ…旅に出発する時点では、その目標のひとつとして木地屋の採集が企図されている。…心川まで行ってみると、心川には木地屋は一軒もなく、もう少し上流の鈴ヶ沢の集落に「とっさま一人居る木地屋の家がある」と教えられる。鈴ヶ沢は過ぎてきたのだが、それに気づかなかったらしい。…先生がなぜ木地屋の家に行き合わなかったか、少し不思議にも思われる」2022/03/27