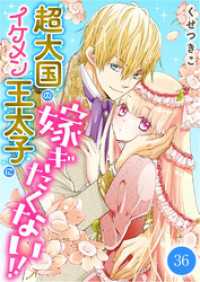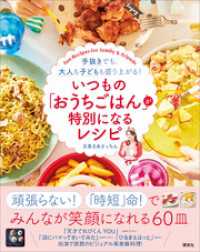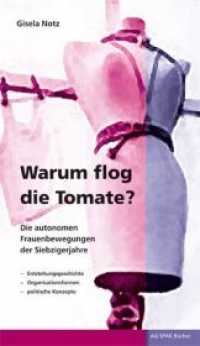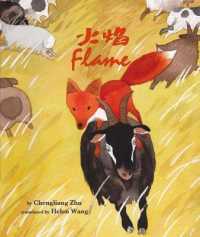出版社内容情報
「対照言語史」という新しい視点で5つの言語の歴史を比較し、「標準化」のもつ意味を多角的に考察する。
内容説明
「正しいことば」はどのように作られるのか?「対照言語史」という全く新しい視点を導入。5つの言語の歴史を比較することを通じて、「標準化」のもつ意味を多角的に考察する。執筆者同士が紙上で知見をやりとりするユニークな構成。
目次
第1部 「対照言語史」:導入と総論(導入:標準語の形成史を対照するということ;日中英独仏―各言語史の概略)
第2部 言語史における標準化の事例とその対照(ボトムアップの標準化;スタンダードと東京山の手;書きことばの変遷と言文一致;英語史における「標準化サイクル」;英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に;フランス語の標準語とその変容―世界に拡がるフランス語;近世におけるドイツ語文章語―言語の統一性と柔軟さ;中国語標準化の実態と政策の史話―システム最適化の時代要請;漢文とヨーロッパ語のはざまで)
著者等紹介
高田博行[タカダヒロユキ]
学習院大学文学部教授。ドイツ語史、歴史語用論、言語と政治
田中牧郎[タナカマキロウ]
明治大学国際日本学部教授。日本語学、日本語史
堀田隆一[ホッタリュウイチ]
慶應義塾大学文学部教授。英語史、歴史言語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shinjuro Ogino
0
私は全くの素人ながら言語について関心がある。本書は、5言語についてその歴史を対照してくれる。ただし精粗は大きい。仏語は海外のクレオール語の話ばかりで国内の言葉の変化については触れていない。独語の標準化は、ルターの聖書の翻訳の役割が圧倒的(目的はキリスト教の普及)。中国は、元、清と異民族の支配にあったが中国語は温存された。ある表現について2500年間の変化を示した表(p211)が興味深い。見ようによっては余り変化していない。英語はノルマン侵攻(1066)の前から標準化の動きがあり、仏の撤退後、標準化は再開。2022/07/21