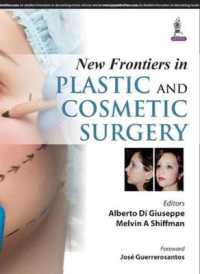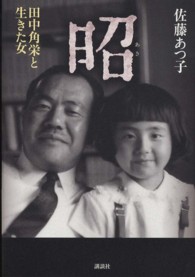内容説明
言語の働きは本当に道具としてのそれだけなのだろうか?それとも、言語には有用・無用にかかわりなく存在するなにかもっと大切な働きがありはしないだろうか?一見、無用とも思われがちな少数民族の言語に私たちはかけがえのない価値、それも当該民族にとってのみならず、この地球上に生きる私たちすべてにとってかけがえのない価値を見出すことはできないのだろうか?そして、そのような価値を見出すことができたとして、私たちはそれを守るために一体なにができるだろうか?本書は、シベリアの少数民族の言語、コリャーク語のフィールドワークを通して、著者がこのことを自分自身に問い続けてきた記録である。
目次
危機言語に取り組むということ(世界の言語は今?;なぜ、危機言語を守らなければならないのか?)
ツンドラの危機言語、コリャーク語―記録保存から復興保持まで(コリャーク語との出会い;豊かな自然の豊かな語彙;目をみはる言語・目をおおう現実;続けてこそのフィールドワーク;現地還元の道を探し始める;ムチギン・ジャジュチウン(私たちの家族)ができるまで)
そしてツンドラへ―言語人類学的研究の最後の可能性を探る(「生きた」コリャーク語をもとめて;ツンドラの生き証人たち;命名の伝統と変容;ことばに映し出されるツンドラの時空;多様な自然資源をあまねく利用する;トナカイをめぐる語彙)
コリャーク語に未来はあるか(先細る生業・先細る言語;それでも守りたい人がいるかぎり)
著者等紹介
呉人恵[クレビトメグミ]
1957年山梨県生まれ。東京外国語大学外国語学部モンゴル語学科卒業。東京外国語大学大学院外国語学研究科アジア第一言語専攻修了(文学修士)。北海道大学文学部助手を経て、現在、富山大学人文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
niko
allomorph
おとや