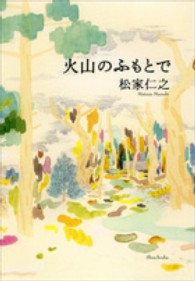- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
北欧の一小国として長い苦難の歴史を歩んできたフィンランドにおいて、文学は常に民族の心の支えとして数多い作家と読者を育んできた。辺境ゆえに世界に開かれた「森と湖の国」スオミ。その豊穣な文学的風土を探る。
目次
民俗詩
スウェーデン支配時代の文学
19世紀文学
1900年から第2次世界大戦まで
戦後のフィンランド文学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
31
カイ・ライティネン氏によるフィンランドの文学の俯瞰。文学史もまた波乱のフィンランド史と無縁ではなく、18世紀末に収集された民謡の起源から始まり、中世スウェーデン支配時代、19世紀ロシア支配時代、そして独立に向けたナショナリズム高揚期から第二次世界大戦期、そして戦後から現代(1980年あたりまで)を網羅。本書の出た93年時点では巻末の邦訳作品リストもまだまだ少ない。1920年代に書かれたエストニアの歴史と民俗をベースにした「狼の花嫁」(Sudenmorsian:マリア・カッラス)はぜひ読んでみたいもの。⇒2025/03/23
うえ
9
「トゥルクに大学が創立され(1640)、その2年後にこの市に印刷機が出現するや、フィンランド文学の条件と方向は大きく変わった。それ以前は完全に支配的であった宗教的な教会用著作は…世俗的で新しい特徴を示すようになった。この大学の最初の教授は大抵がスウェーデン人で、その作詞は大方スウェーデン語であった…スウェーデン語劇の父はヤコブ・クロナンデル(『波濤』、『ベレ・スナック』)で、フィンランド劇の方はユスタンデル(1623-78)である。その『放蕩息子』という劇のスウェーデン語からの訳は今は残っていない。」2021/05/09
圓子
2
事実、読もうとおもっても手に入るものがなかなかないのだよ。2013/11/18
の
1
文学的にあまり有名では無い所を知りたいがために興味半分で読んだのですが、そのため神話から現代文学まで手堅く網羅しているのが有り難かった。スウェーデン・ロシアに支配され、20世紀になってやっと独立した国であるため、文学における民族意識はかなり薄いのですが、ロマン主義的な自然賛美は言語の使用法も含めて多く読みとることができます。フィンランドと聞くと真っ先にヘヴィメタルが思い浮かんでしまう人間ですが(北欧メタル好き)、北欧文化への憧憬もあるので少しずつ勉強していけたらまた違った目線で楽しめるようになれそう。2011/03/09
Hiroshi Minami
0
比較的薄い本であるが、コンパクトに纏まっていて、重宝する。2012/06/11