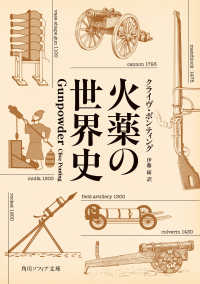出版社内容情報
ヤーコブソンの構造主義言語学は音韻論の分野をはじめとして、言語分析の極めて有力な武器である。名高い「提議」他を収録、その方法を明らかにする。
内容説明
構造主義言語学の精粋。20世紀を代表する言語学の巨匠ロマーン・ヤーコブソンの浩瀚な著作の精華を全3巻に収めたわが国初の選集は、言語学固有の主題を展開する本巻で完結する。1928年亡命先のチェコでプラーグ学派を代表して第1回国際言語学者会議へ提出し、デビューを飾った名高い「提議」を初め-「音韻的言語連合」「一般格理論」、「言語学的概念“弁別特徴”」等の言語学史上に輝く名論文を収録。彼の言語分析の方法を明らかにする。
目次
第1回国際言語学者会議への提議
音素と音韻論
史的音韻論の諸原則
音韻的言語連合について
音韻的言語類縁性の理論について
ロシア語動詞の構造について
一般格論理への貢献
ロシア語の活用
ロシア語の性パターン
ロシア語の語幹接尾辞と動詞―アスペクトとの関係
ゼロ記号1
ゼロ記号2
言語学の主題としての失語症
言語学的概念「弁別特徴」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
5
スラブ語系言語分析が中心の本書だが、従来の言語学が別個と見な指摘た語用論的な発話と象徴的な文法を結びつけた著者の分析が、意味と機能を同時に把捉するために用意した一連の概念を含む主要論文が収録されている。コードとメッセージという情報理論のコミュニケーションモデルをベースとした著者は、主格(が)と造格(によって)を弁別的コードとし、「指示詞(この)や代名詞(私)を転換子と捉え、さらに言語「周縁」で変化するコンテクストとの動的関係を言語記号の類像性や指標性として指摘して、言語学を記号論へ拡張する可能性を示した。2021/12/03