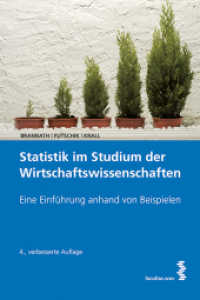- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
中世の無常観は蓮如の「紅顔むなしく変じて白骨となる」にみられ、正倉院文書・敦煌出土文書などにさかのぼります。さらに六世紀頃、無常観を悟るために僧が白骨を観想する図がシルクロードの石窟寺院の壁画にあります。野辺に白骨がころがる時代から、これを尊重・保存する建墓の時代を経て、再び無墓の方向に揺れ動く葬送の変容をたどります。
目次
まえがき―「腐敗屍骸墓」はなぜ作られたのか
序章 安楽死を祈願する―人道の苦相(生前相)
第1章 風葬、樹木葬、散骨葬
第2章 白骨観の系譜
第3章 中世の九相観説話
第4章 髑髏の話
あとがき―「無墓制」と「遺骨崇拝」
著者等紹介
岸田緑渓[キシダリョクケイ]
昭和20年島根県生まれ。元セント・アンドルーズ大学客員研究員。現在、浄土真宗本願寺派僧侶(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐倉
10
古代、中世、近世、そして現代にいたるまでの日本人の死との付き合い方や考え方を九相図などを中心に読み取っていく。腐りゆく死体を見ることで現世の執着を断つ九相観の修行がシルクロードの石窟や天台智顗の『摩訶止観』などには読み取れるが、浄土真宗の蓮如による『白骨の御文』では腐敗が飛ばされて生者から骨へとなる無常観に主眼が移る。九相図の題材として描かれる小野小町と壇林皇后の題材としての違い。前者は驕慢な美女の変貌を描く男性主体の図、後者は女性が主体的に悟る物語となっており、成立的には小町→檀林皇后の順になるらしい。2023/11/19
-

- 和書
- ヨーロピアンバンキング