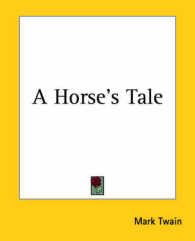内容説明
旅する文人画家と「真景」の発見、さらには自然への共感から誕生する西欧風景画。池大雅/与謝蕪村/レンブラント/フェルメール/司馬江漢/浦上玉堂/歌川広重/谷文晁/田能村竹田/渡辺崋山/プサン/コンスタブル/ターナー/T・ルソーほか。
目次
第1章 画家たちの旅―剥き出しの自然へ
第2章 自然に分け入る―本草の思想
第3章 探訪の眼差し―真澄、牧之、忠敬
第4章 文人画家の自然への視点
第5章 西欧の風景画誕生と進展
第6章 名所絵と浮世絵風景版画
第7章 「真景」と肉眼の視点
第8章 眼差しの個性
著者等紹介
山梨俊夫[ヤマナシトシオ]
1948年、神奈川県横浜市生まれ。1972年、東京大学文学部美学芸術学科卒業。1976年、神奈川県立近代美術館学芸課勤務。1992年、同館学芸課長、2002年、同館副館長を経て、2004年に同館館長。定年後も非常勤館長として勤務。2011年、国立国際美術館館長、現在に至る。日本、フランスの近現代美術を主な専門領域とし、数多くの展覧会企画を担当する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kn
0
第一巻に続いて、人が世界に触れ、世界と対峙する様々な例を東西で章を立てて見ていく。伊能忠敬の測量など、「風景画」というくくりだけでは漏れてしまいそうなところも丁寧に追うことで、時代によって人が世界を見る眼差しの変化を知ることができる。 後半はようやく今私たちが「風景画」と聞いてイメージする典型的な作例(コンスタブルやバルビゾン派)が登場してくるが、それは19世紀のこと。いま当然のものとして受け入れている「風景画」という概念や、現地でのスケッチから本画を制作するという流れが意外に新しいことに気がついた。2021/01/25