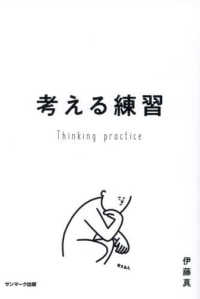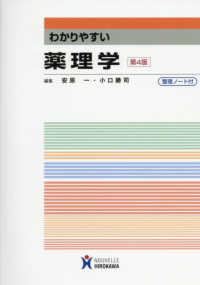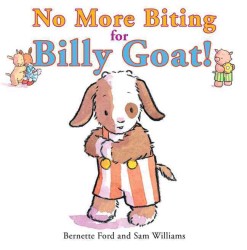内容説明
2020年、アベノミクス後の日本。没落する中産階級!!「一億総中流」社会を支えたサラリーマンたちはいま二極分裂し、その大部分が下層に飲み込まれようとしている!
目次
第1章 アベノミクスの展開と終焉
第2章 世界経済停滞の流れを読む
第3章 「近代資本主義の終焉」という大転換
第4章 一億総中流の「奇跡」はいかに実現したか
第5章 二〇二〇年東京オリンピックを迎える日
第6章 インターネット社会が変える私たちの生活
第7章 サラリーマンたちが下層化していく
第8章 「ゼロ成長」時代のこれからの日本
著者等紹介
榊原英資[サカキバラエイスケ]
1941年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業後、大蔵省に入省。ミシガン大学で経済学博士号取得。IMFエコノミスト、ハーバード大学客員准教授、大蔵省国際金融局長、同財務官を歴任する。為替・金融制度改革に尽力し、「ミスター円」と呼ばれる。1999年、退官後、慶應義塾大学教授、早稲田大学教授を経て、青山学院大学教授、財団法人インド経済研究所理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たか
4
日本もアメリカの後を追って格差社会が到来。特に相対的な貧困率が高い。 成長社会から成熟社会に移り、サラリーマンはどうすれば生き残ることができるかを問う内容。何かスペシャリストな分野を身に付けつつ、ゼネラリストになる方向が必要かもしれない。 時間は有限。無駄にすることなく、有意義な時間を過ごしたい。 やるしかない❗2015/10/26
HMax
3
失われた20年ではなく、先進国に特有のゼロ成長の時代に入り、国はアベノミクスではなく、低成長に則した現在とは逆の高福祉政策(社会保障費の80%を高齢者を主な受給者)に舵を切り、個人レベルではどのようにして豊かな生活を享受するかを考えるべき時代突入しているといことを様々なでーたで検証しています。サラリーマンもこれからは中印との競争だけでなくAIとの競争もあり、特殊技能で勝負する時代。自分に磨きをかけよう。 驚いたのは平均年収のピークが日本では1997年、米国では何と1973年。2016/04/22
田中峰和
3
低成長とデフレは先進国共通の現象である。アベノミクスなるまやかしの経済効果は経営者層をより富裕にするが、インフレによる実質賃金低下は中小企業のサラリーマンにより厳しい生活を強いる。ここにきて、マイナス金利政策まで始まった。第3章で引用される水野和夫氏の「近代資本主義の終焉」。2%以下の低金利が長期間続く状況を利子率革命と呼んだ水野氏。マイナス金利の現状は終焉どころか崩壊だ。そのうえGDPまでマイナス成長。年金運用の失敗は国民の老後を脅かす。フロンティアが消滅した世界経済、先進国経済はデフレを活用すべきだ。2016/02/25
ドリアン・グレイ
0
どこかでみたことのある日本の経済問題の寄せ集め2016/12/26
謙信公
0
極端な高福祉高負担は反対だが、年金等を保険式から税方式にすることは、大賛成。そのためには、消費税アップも仕方がないとは思うが、今は時期尚早。アベノミクスで経済発展を加速してからでないと、抵抗が大きすぎる。消費税は、金持ち優遇で弱者に厳しいなどという人がいるが、そうは思わない。弱者より金持ちの方が消費するのだから、負担は大きくなり、富の再分配はなされるのではないか。みんなで負担し、弱者には手厚く保護する。高齢者の年金や子供への手当などを増やす。どのあたりが最適かは、頭のいい官僚が試算すればよいことだ。2016/11/22