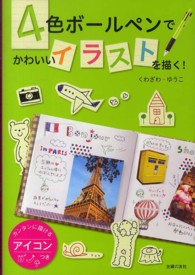内容説明
理由のない行動はない。その理由を活かして人を変える技術。脳科学は理論から実践へ。
目次
脳の報酬作動系を育てる
スキル化された言葉と表情
ワーキングメモリトレーニング
教師を育てる“内なる教師”
教師を育てる自己申告型評価システム
対応スキルの基礎基本
発達障害児がいるクラスの人間関係づくり
親は教師を頼りにしている
保護者との対話スキル
NG対応で子どもは追いつめられる
発達障害はワークングメモリ低下×対人的不適応
著者等紹介
平山諭[ヒラヤマサトシ]
筑波大学大学院博士課程で心身障害学を学ぶ。「言葉」と「表情」と「栄養」の統合に着目した臨床活動を展開。専門は、脳科学教育臨床、臨床発達心理学、カウンセリング(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
るい
5
この本を読んだ後、セロトニン5を意識してはいるが、とっさの時に叱ったり厳しくしたりしてしまう。優しくしたら甘えるのではないか、なめられるのではないかという恐怖があった。しかし、もし子どもが甘え過ぎるのならば、満足度が不足していることをアピールしているらしい。私が相手にしているのは12歳以上の子どもであり、ここに書かれたように関わってもストレートには入らないことも多い。しかし、とっさの時でも、子どものプライドを立てるようにし、優しい口調、言い分を聞くといったことを心がけていきたい。まだまだ修行が必要だ。2015/01/31
るい
3
授業をしていて「しづらい」と思わせる発達障害の子どもたち。この本を読むことで、ADHD、PDD、LDといった発達障害の子ども達の特徴と、脳内でどんな物質が足りていないのか、それを補うためにはどういう指導が有効なのかを知ることができた。教師必読の一冊。「見つめる」「ほほ笑む」「話かける」「ほめる」「触れる」といった『セロトニン5』スキルを使い、ワーキングメモリを増やすトレーニングをし、生徒を育てていきたい。2014/06/22
るい
2
6年ぶりに再読。あの頃、新鮮だった用語の一つ一つが、自分の中で当たり前になっていることに驚く。しかし、この本に出会わなければ、今、これほど発達障害の子どもたちと楽しく良好な関係を築くことはできなかっただろう。私の目の前にはADHDの生徒が多いのだが「見通し」「時間制限」という手立てを忘れていた。さっそく実践したい。また、ADD気味の生徒にこそ、セロトニン5が重要と知ったので、これも取り入れてみる。読み返した時々で学びが大きい。何度読み返しても勉強になる一冊。2021/06/11
Ken
1
1.ほめ方5つ。①短いフレーズで元気よく。②名前を入れて。③成長や達成を実感できるようんじ。④事実を話題にして,微笑みながら。⑤期待を込めて(~だと嬉しいな) 2.ノルアドレナリン系スキル(緊張し,注意力・意欲がアップ)…のぞきこむ。(これは,インパクトがある) (感想)良書。繰り返し読みたい。読むごとに発見があるはず。 2013/01/21
良さん
0
生徒にとって価値ある教師になるための具体的な方法がここにある。セロトニン5は教師が絶対に知っておかなければならないこと。 1見つめる、2ほほ笑む、3話しかける、4ほめる、5触れる、これは暗唱して、子どもたちに対してできたかどうか毎日確認したい事柄だ。2012/01/08