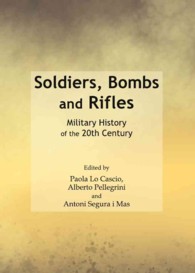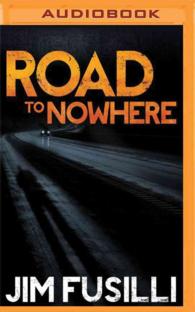内容説明
20世紀を代表する映画監督の一人アンドレイ・タルコフスキー(1932‐1986)。その映画作家としての名声の陰に一個人としての人生の変転があり、それが時代の刻印を帯びていたことを忘れてはならない。本書は、彼の運命を織り成した時代状況と人間関係を、広範な資料をもとに再構成している。
目次
第1章 始まり(創作の準備期間;音楽美への目覚め ほか)
第2章 映画界へ(「雪解け」使命の自覚;突然の栄誉 ほか)
第3章 芸術と人生(アンドレイの受難;「停滞の時代」と映画産業の隆盛 ほか)
第4章 幻滅と解放(「ゾーンは人生だ」;イタリアのロシア人 ほか)
著者等紹介
西周成[ニシシュウセイ]
1967年生まれ。早稲田大学第一文学部文学科卒業、同大学大学院文学研究科修士課程修了(映画学)。全ロシア国立映画大学大学院修了(Ph.D.)。現代ロシア映画関係の論文・批評、映画字幕等、多数。2009年より合同会社アルトアーツ代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
秋 眉雄
10
かなり駆け足の一冊でした。後半に行けば行くほど駆け足。しかしながら、なんだかもの凄く筆者の執念を感じさせる、そういう一冊でもありました。「仕事がしたい、それだけでいい。仕事!イタリアの新聞が天才と讃えた監督がなんの仕事もできないでいるとは、あきれた話ではないか、犯罪ではないのか」自分の仕事をするということは、最も大切なことの一つであり、それが出来るというのは最も幸せなことの一つだと思います。2016/03/26
MO
6
監督の人生年表。これで作品の理解が深まるものでは無いし人格がよくわかるわけでも無いのですが、当時のソ連政府下でいかに創造が上手くできないかは慮られた。後年に神秘主義に惹かれていったのは個人的にツボで、ルドルフ・シュタイナーに関する映画製作を想っていたらしく、それはぜひ観たかった。いくら残念がっても新作はなく、数えられるだけの作品しかないのだけれど「死ののちもこれらの人々と対話を続けていけるのだと考えると、私は無上に幸福だ」とある。タルコフスキー監督、僕は何度でもあなたと対話しますよ。2022/01/04
die_Stimme
2
『アンドレイ・ルブリョフ』あたりまでがかなり詳しく書かれている。タルコフスキーの中での思想や信仰、神秘主義との関わりやその作品への影響についてもっと知りたかった。あとは、タルコフスキーは寡作でその一因はゴスキノによる検閲で製作許可が降りなかったことというのは分かるけど、ゴスキノによる検閲がもう少し具体的にどういうもので、タルコフスキーの構想のどのあたりが検閲に引っかかっていたのか、とかも。あとタルコフスキーの神秘主義とロシア正教の教義とはどれくらい異なるもので、それらと検閲との関係とか……2021/05/22
ハンギ
0
タルコフスキーの作品はまだ一作も見ていないけど、なかなかソ連の映画事情も含めて面白かった。検閲と圧力があるにもかかわらず、国家主導の元、西側諸国にも認められる、作品や監督を輩出できたのは興味深い。なぜそれが可能かというのは、ソ連の指導部や当局が知識人層の不満を和らげるためにいろいろと配慮していた、というのが著者の分析だった。どんな体制でも文化のために戦う人はいるんだなあと思った。2014/09/02
ra0_0in
0
専門家ではないので、本書が呈示するタルコフスキー像をどう評価すべきなのかは分からないのだが、難解な作風で知られる巨匠に対して誠実に、神秘化を注意深く排除して、歴史化するという姿勢には非常に好感を持てた。結局のところ、「観察=リアリズム」と「詩=ロマンティシズム」との矛盾を止揚できないタルコフスキーの作品世界とは、彼の個人的幻想の客観的相関物以上でも以下でもないのだなぁと思った。つまり、彼ほど「好きな人は好き」な映画作家はいないわけで、こうした作家がソ連に誕生した事実を後世の映画史はどう評価するのだろう。2014/05/26