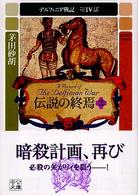内容説明
100年の歴史を有するプラネタリウムについて、その誕生から現在までの移り変わり、しくみや楽しみ方、魅力などを、プラネタリウムの製造を行うメーカーの社員や、プラネタリウム施設の運営や投映(解説)を行う解説員が、わかりやすく紹介しています。この本を通じて、より多くの方々にプラネタリウムに興味を持っていただき、実際に訪れていただければ幸いです。
目次
1 プラネタリウムのきほん(「プラネタリウム」の名前の由来を教えてください。;プラネタリウムを作った目的はなんですか? ほか)
2 もっと知りたいプラネタリウム(プラネタリウムの投映機はどのように進化してきたの?;プラネタリウムの補助投映機はどのように進化したの? ほか)
3 プラネタリウムをつくる(プラネタリウムを作っている会社っていくつあるの?;プラネタリウムを作るのにどのくらいの期間がかかるの? ほか)
4 世界のプラネタリウムと投映内容(プラネタリウムは、世界にどのくらいありますか?;有名なプラネタリウムを教えてください。 ほか)
5 解説者のしごととプラネタリウムの楽しみ方(プラネタリウムの解説者になるには、どんなスキルや能力が必要ですか?;解説者は投映時以外どんなしごとをしているの? ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
200
1923年10月21日、プラネタリウム初号機「カール·ツァイスⅠ型」がドイツ博物館で試験公開されて、今年でちょうど100周年。東洋初のプラネタリウムは、1937年大阪市立電気科学館。現役のアジア最古投影機は1960年に明石市立天文科学館に設置されたカールツァイスイエナUPP23/3。世界最大直径35mのドームスクリーンを持つ名古屋市科学館など、日本にも魅力的な施設は多い。国産プラネタリウムメーカー3社(コニカミノルタプラネタリウム、五藤光学研究所、大平技研)には、これからも頑張ってほしいです。2023/09/08
takao
1
ふむ2023/10/23
-
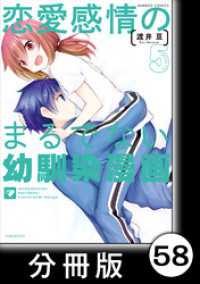
- 電子書籍
- 恋愛感情のまるでない幼馴染漫画【分冊版…
-

- 電子書籍
- AneLaLa ヒノコ story03…