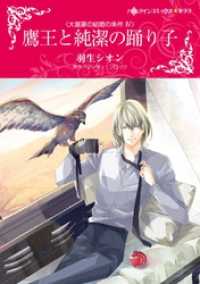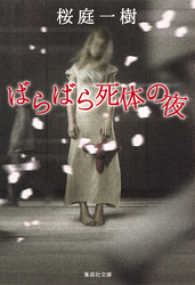出版社内容情報
地球のいとなみが長い時間をかけて生み出した結晶である鉱物。
人は昔からその鉱物を見出し、加工して各種の道具を作り出したり、あるいはその美しさに特別な価値をおいて寵愛してきた。鉱物と人類の文明・文化は切っても切れない関係にあると言っても過言ではない。
本書は、そうした鉱物の文化的・歴史的逸話から採集時のみやげ話まで、人と鉱物の織りなすエピソードを5つのテーマ、50のお話で紹介する、読む鉱物図鑑である。
産経新聞夕刊紙上で連載されていた人気コラム「宝の石図鑑」を大幅に改訂増補し、250点以上の撮りおろし鉱物写真を収録する。
内容説明
鉱物の文化的・歴史的逸話から採集時のみやげ話まで、人と鉱物の織りなすエピソードを5つのテーマ、50のお話で語る、読む鉱物図鑑。250点以上の鉱物写真を収録!
目次
第1章 名前をめぐるストーリー(ガーネット/ザクロ石―初めて見た赤い星;パイライト/黄鉄鉱―愚か者には見分けがつかない ほか)
第2章 フィールドのみやげ話(デュモルチェライト/デュモルチ石―宝は思いがけないところから;クォーツ/ロッククリスタル/石英/水晶―ありふれた鉱物でも出会いは特別 ほか)
第3章 文化の裏に鉱物あり(カイヤナイト―藍晶石―イーハトーヴの夜の青;ベリル/エメラルド/緑柱石―天然ばかりが全てじゃない ほか)
第4章 研究者と産地に敬意を(ヘンミライト/逸見石―日本産の派手なやつ;キムラアイト/木村石―見た目は地味だが光を届ける ほか)
第5章 十石十色(カルサイト/方解石―鉱物界の便利屋;アラゴナイト/あられ石(アンモナイト化石)―かつて貝だった鉱物たち ほか)
著者等紹介
藤浦淳[フジウラジュン]
1964年、大阪府生まれ。岡山大学文学部卒。1989年産経新聞社入社後、主に事件・事故・災害担当として大阪本社などで勤務。社会部デスク、和歌山支局長、文化部長などを歴任。小学校6年生から鉱物採集に目覚め、仕事のかたわらも断続的に続ける。2000年に公益財団法人・益富地学会館の門をたたき、以降主任研究員(当時)藤原卓氏の全面的な協力を得て鉱物に関する1面連載「鉱(いし)の美」(2006~2007年、13編)や、藤原氏の寄稿「鉱物(いし)の故郷」(2008~2010年、59篇)の編集を行う。2012年からは自著の夕刊連載「宝の石図鑑」を開始、7年間で238編を著す。現在は清風学園清風中学校・高等学校常勤顧問を務めるかたわら、益富地学賞審査委員、大阪大学総合学術博物館非常勤研究員、大阪経済法科大学客員教授、一般財団法人・防災教育推進協会理事、貝塚市教育政策アドバイザー、一般財団法人・貝塚市文化振興事業団理事ほか多数を兼任している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
なつ
鯖
ぽてちゅう
みやび