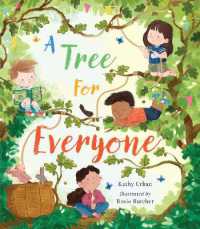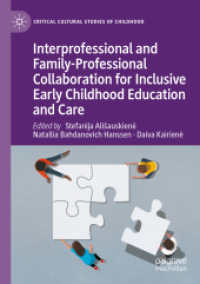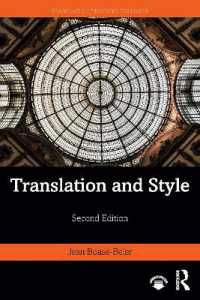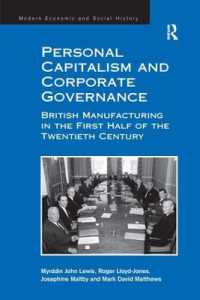出版社内容情報
20世紀という時代を切り開き、その後の世界の動向を決定づけた歴史的大事件。
内容説明
本書は、視覚データをふんだんに盛り込むことによって、読者とロシア革命との間の対話のよき導き手となることだろう。ソヴィエト期の国家史の書物と並んで、農民の日常生活史の仕事もある著者ならではの、バランスがとれた内容である。
目次
第1章 戦争から革命へ
第2章 2月革命:「栄光の5日間」
第3章 世界一自由な国
第4章 革命か、戦争か
第5章 革命は続く
第6章 10月革命
著者等紹介
ヴェルト,ニコラ[ヴェルト,ニコラ][Werth,Nicolas]
現代史研究所(国立科学研究センター)の研究員。歴史学教授資格者。ソ連史の研究にたずさわっている
石井規衛[イシイノリエ]
1948年生まれ。東京大学文学部卒。同大学院人文科学研究科博士課程修了(西洋史)。東京大学文学部教授。専攻はロシア近・現代史
遠藤ゆかり[エンドウユカリ]
1971年生まれ。上智大学文学部フランス文学科卒
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
春ドーナツ
19
ルソーの「社会契約論」と本書を併読した。前者は喫茶店書見台、後者は寝床転々。ルソーと言えば「一般意思」のような気がする。「国家の全構成員の変わらぬ意思が一般意思である。一般意思によって彼らは市民であり、自由なのである」マルクス経由レーニン・ビジョンにパラフレーズすることは可能なのか。そんなことを考えながら革命の展開を追っていたと思う。けれども私にとってマルクスはブラックボックスなのだった(単に未読)。「実験」という文言には抵抗を覚えるが、それは74年続いた。表紙はエイゼンシュテイン監督「十月」のポスター。2019/09/04
maja
11
当時の街や村、戦地の人々の様子、写真やポスター、風刺画などが数多く掲載されて流れと空気感が捉えやすく作られている。後ろに年表と用語説明。「オクトーバー」物語ロシア革命/チャイナ・ミエヴィルと合わせて読む。 2019/09/24
向う岸
9
第一次世界大戦への厭戦感と食糧不足が原因で帝政を終わらせ民主化を行った二月革命。工場では労働者が労働時間の短縮など労働環境の改善を求め、農村では地主が所有する農地の解放など格差の是正や再配分が当事者から求められて実施された。臨時政府と各勢力の権力闘争が繰り広げられるがレーニン率いるボリシェヴィキが政権を握ったのが十月革命。レーニンと言えども沸騰する大衆の熱気を無視出来ず彼らの要求を政策に盛り込んだ。革命においては軍を掌握するかが重要。デモ隊への発砲を拒否しむしろ軍が民衆側に加担したことが革命を推進させた。2016/08/18
アトレーユ
6
『静かなドン』を読んでいて、革命側と反革命側があまりにもごっちゃになりすぎて、わけがわからなくなったのでお勉強。ロシア革命の概略がわかった…気がする☆2015/10/06
Fumitaka
5
二月革命から十月蜂起までの経緯を当時の写真や檄文などを交えつつ解説。石井規衛先生の序文では、ロシア革命という事件を過度に神格化せず、また二十世紀初期を切り開いた大事件とする(p. 1)とする指摘。ロシア帝国が「さながら地球の縮図」という叙述は、コトキンのスターリン伝の最初の方(S. Kotkin, “Stalin: Paradoxes of power, 1878-1928”, Penguin Press, 2014, p. 1)を思わせる。ひょっとしてコトキンは日本に滞在中にここを読んだのだろうか。2023/06/06