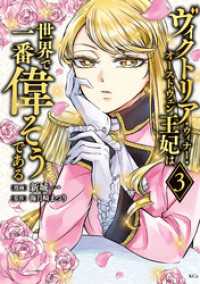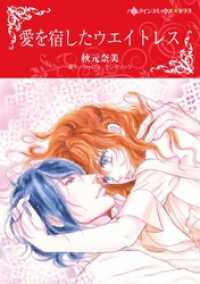出版社内容情報
生物の「多様性」と、それが失われつつあることへの危惧が語られて久しい。この地球上にはさまざまな生物が息づき、互いに繋がり合いながら生きている。その豊かな繋がりが失われつつあることへの危機感は、人間の心についても言えるのではないだろうか。
人は一人ひとりみな違い、それぞれが固有の人生を生きている。複雑で矛盾だらけの人間の心を扱うには、一人の人間の場合ですら、その時々において多様なアプローチが求められるはずである。しかし現実には、こころの臨床の動向は、豊かな多様性に対応する方向に進んでいるとは言いがたいように思われる。
昨今、生物学的精神医学の急速な進歩にともない、精神科医の多くは自然科学の新知見の吸収に追われて、幅広い領域の知を取り入れる余裕がなくなっているようにも見みえる。自然科学の知見だけではなく広く人文科学を含めた他領域の知は、心の多様性に向き合う臨床家のセンスを格段に豊かにし、深めてくれるものではないかと著者は語る。
本書は、人間存在を心身の相対的な枠組みのなかで総合的に理解しようとしたC・G・ユングの考え方をもとに、著者自身の臨床観を簡潔に紹介しながら、さらにはユング派精神療法の真髄とも言える夢分析の実践事例のプロセスを丹念にたどった貴重な一書である。演奏時の手の震えを主訴として訪れたヴィオラ奏者は、著者に自身の夢を語るなかで自らの内面にある問題と自分に起こっていることの意味に気づき、無意識の力を借りながらしだいに薬の助けなしに演奏ができるようになっていった。セラピストと患者とが対等の立場で心の交流を行うユング派のセラピーの様子が、じつに生き生きと描かれている。
最後に著者は、すべての臨床家が、目の前にいる患者から真摯に学び、人真似ではない独自の臨床世界を築いていくべきであることを力説している。すべての人の人生に意味があり、すべての臨床家が作り出した独自の臨床ワールドに意味がある。本書は、豊かな心の「多様性」の実現のために書かれた一書であるとも言える。
[目次]
第一章 ユング派精神療法
1 ユングにとっての無意識
2 ユング派精神療法の特徴
3 ユング派精神療法の実際
第二章 ユング心理学を診療に生かす
1 はじめに
2 無意識の神話産生機能と自己治癒力
3 個人神話の創出
4 全体性の追求
5 おわりに
第三章 西洋人とのユング派夢分析の実際
1 はじめに
2 事例呈示
3 おわりに
内容説明
それぞれの人生をいかに見て、いかに意味づけるか。眼前の患者から、その患者にだけ通用する理論を見いだそうとするユング派精神療法。その要諦と実践内容をつまびらかにする。
目次
第1章 ユング派精神療法(ユングにとっての無意識;ユング派精神療法の特徴;ユング派精神療法の実際)
第2章 ユング心理学を診療に生かす(無意識の神話産生機能と自己治癒力;個人神話の創出;全体性の追求)
第3章 西洋人とのユング派夢分析の実際(事例呈示)
著者等紹介
武野俊弥[タケノシュンヤ]
1953年東京に生まれる。1978年東京医科歯科大学医学部卒業。同大学神経精神医学教室勤務。1980年四倉病院勤務。副院長・院長を歴任。1988~1991年スイス・チューリッヒのユング研究所に留学し、ユング派分析家資格を取得。1992年東京都新宿区に精神療法・精神分析専門のクリニックを開業。現在、武野クリニック院長、医学博士、精神科専門医、精神保健指定医、産業医。ユング派精神分析医(国際資格)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Gotoran
あい