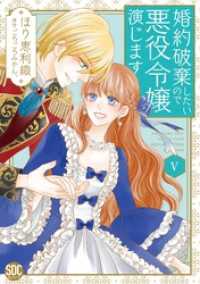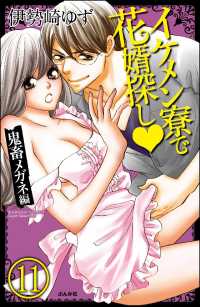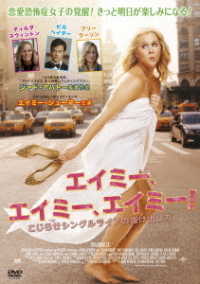出版社内容情報
日本近海で見られるクラゲ、国内の水族館で見られる海外産のクラゲを含め約110種を紹介しています。
日本近海で見られるクラゲ、国内の水族館で見られる海外産のクラゲを含め約110種を、単なる図鑑写真だけでなく、成体になるまでの成長過程の写真もあわせて紹介するほか、クラゲの科学的な魅力をふんだんに紹介します。また、クラゲカレンダーやシーズン、見られる地域など、さらに関心を持った人にも満足できる内容です。本書のように、クラゲの成長する過程を掲載している書籍は、これまでにありません。
【著者紹介】
現在北里大学海洋生命科学部で講師を務め、現在クラゲの研究をしてます。前職は海洋研究開発機構、江ノ島水族館勤務。
目次
刺胞動物門(鉢虫綱;十文字クラゲ綱;箱虫綱;ヒドロ虫綱)
有櫛動物門(有触手綱;無触手綱)
クラゲの採集と飼育
著者等紹介
三宅裕志[ミヤケヒロシ] [Lindsay,Dhugal]
1969年大阪府東大阪市生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。農学博士。海洋研究開発機構、新江ノ島水族館を経て、北里大学海洋生命科学部講師、海洋研究開発機構招聘研究員、新江ノ島水族館飼育アドバイザー。クラゲ類および深海生物の長期飼育を通じた研究を主に手がけている
リンズィー,ドゥーグル[リンズィー,ドゥーグル]
1971年オーストラリア北東部ロックハンプトン市生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。農学博士。海洋研究開発機構海洋生物多様性プログラム技術研究副主幹。クラゲ類を代表とするプランクトンの生態学及び分類学を通じた多様性研究をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遠い日
おおた
あっくん
みか
ひつじのよう