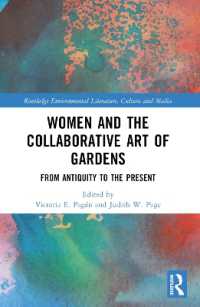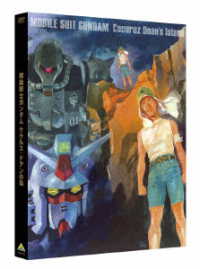出版社内容情報
古来よりやきものには様々な文様が施されてきました。
それらの文様はやきものの絵付け技法とともに進化し、やきものを単なる器としてだけでなく、美術品として愛でる対象にまで昇華させました。
本書では、主に日本のやきものに施されてきた約100種類もの文様を、その模様の意味や時代背景などとあわせて紹介します。
また、各絵付け技法や器面へのレイアウト方法についても、下図などの資料とともに解説します。
鉄絵や染付、色絵などの伝統的な文様から、近現代の作家の文様まで網羅した、資料性が高く、やきものの文様への造詣を深められる充実した一冊です。
内容説明
古来からやきものに描かれてきた文様を100種取り上げその意味や歴史的背景、鑑賞のポイントなどを解説しました。器を美術品へと昇華する「装飾」としての力はもちろん、生活を愉しむ人へ「集める喜び」を教えてくれる存在でもある―そんな文様の魅力を知ると、器がもっと好きになります。
目次
第1章 やきものの文様の変遷
第2章 やきものの文様
第3章 近代の巨匠の文様づくり
第4章 文様の図案
第5章 文様の構成
第6章 装飾技法の基本
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佳音
85
無知なもので、図書館で借り、ウチにあるやきものの文様と照合するのがご時世引きこもりの楽しみとした。100均等大した物があるわけではない。文様には縁起や願いが込められているが、知らぬ事も多く、感心したり、使い方について反省したり。面白い。 追記: 本書に掲載のやきものはほぼ全て骨董です。年代別の蕎麦猪口など骨董についての知識が学べますので、本書の趣旨と違うと思うけど、先述したように文様探しみたいな楽しみを見つけてみました。既読された方がいぶかしがるかもしれないので、一応追記します。2021/04/10
遠い日
3
子どもの頃実家にあった古い食器の数々(普段使いの食器とは別にされていて、多くの人を呼ぶ時、<例えば冠婚葬祭的な>、に引っ張り出されてくる)は粗悪なものだっただろうが、いろいろな文様が記憶に残っている。その意味や特徴、自分の好みなど、こうして見ていくとわかってくる。わたしはやっぱり色絵より、藍の染付けが好きなんだと再確認。2021/04/09
Koki Miyachi
2
陶芸好きにとって、興味があるテーマやきものの文様の本。文様を種類別に分類して、成立の背景、バリエーション、作品の事例などをカラー写真等でビジュアルに紹介。文様のバリエーションもグラフィックで解説されていて便利です。文様の意味、作者の意図を知ると、より深くうつわを愛することができそうです。2025/02/06
小椋
2
以前同じシリーズの本を読んで分かりやすかったので購入。色んな文様は眺めているだけでも楽しいです。中にはデフォルメがききすぎていて「いや、分かんないでしょ!?」と思ったものもありましたがそれもまた面白い。器を選ぶ楽しみが広がりそうです。2021/03/30
Go Extreme
1
やきものの文様の変遷:縄文土器 弥生土器 須恵器 六古窯 桃山陶 有田焼・九谷焼の磁器 京焼 薩摩焼 明治の陶芸 近現代のやきもの やきものの文様 近代の巨匠の文様づくり:富本憲吉の文様づくり 坂谷波山の文様づくり 文様の図案:アイデアスケッチ 平面図 展開図 縁文図 図案と試作品 文様の構成:枠取り 窯絵・画中画 反復・連続 絵画的 蕎麦猪口の文様構成 装飾技法の基本:素地への装飾 鉄絵 染付 色絵・上絵 金銀彩 釉下彩・彩磁 2021/03/29
-
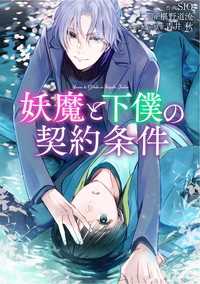
- 電子書籍
- 妖魔と下僕の契約条件【タテスク】 第1…