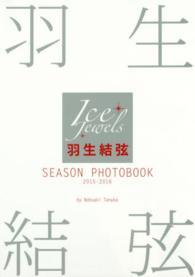内容説明
鉄道ジャーナルが贈る知られざる鉄道物語。近代鉄道100年にわたる手書きのロマン。駅名標・車輛標記・ナンバープレート、鉄道文字の源流をたどる。
目次
文字が語る「サービスの心」鉄道書体すみ丸ゴシック―「すみ丸」を守り育てた須田寛氏の述懐を踏まえて
よりよい文字へのこだわりが生んだ偶然 現代に生きる「すみ丸ゴシック」―半世紀前の手書きのよさに止まらない普遍的な価値を獲得
昭和の広告看板にも重宝された ホーロー引きの駅名標を作る―国鉄からも受注した工場で訊く
鉄道国有以来の文字が今も生きる 車輛の標記―車輛工場の伝統を受け継ぐ大宮総合車両センターで訊く
蒸気機関車の前面を重厚に飾る青銅の板 ナンバープレートと文字―図面で指定された国鉄書体にも鉄道工場ごとの出来栄え
もうひとつの書体ものがたり 営団地下鉄のサイン文字―直感的な読みやすさを追求したゴシック4550書体
都市の景観に一体化する百年文字 ロンドン地下鉄とジョンストン・サンズのように
著者等紹介
中西あきこ[ナカニシアキコ]
1975年神奈川県生まれ。二松学舎大学大学院修了。大学時代より書道を学ぶ。月刊『旅と鉄道』(鉄道ジャーナル社)で地下鉄路線を地上でめぐる「二駅歩き」の連載をきっかけに地下鉄に残る旧い文字に興味を持つようになる。昭和の時代感覚あふれる看板や書体・フォントをたずねてさらに取材を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
32
日常目に触れ続けてきた駅名や構内表示の文字の世界、特に今もJR東海で使われ続ける「すみ丸ゴシック」と旧営団地下鉄の専用書体に注目しレポートしていく。自分の目にへばりついてるウロコの分厚さに気付かされる。鉄道好きで、かつ書体は仕事で使い続けてきた(同様にデジタル化を経験してきた)にも関わらず、全く知らなかったし気づけもしなかった。◇国鉄で洗練されてきたこの書体を愛するJR東海の元社長(民営化を成功させ産業観光を提唱した人としても名高い)と、書体を完成させたデザイナー。この人が縁を結び実現した対面にほっこり。2018/02/10
マカロニ マカロン
17
個人の感想です:B。地元図書館のヤングスタッフ主催のビブリオバトルでのチャンプ本。ユーモアを交えた楽しい紹介だったので、読んでみたが、鉄オタの中の「文字鉄」と言われるジャンルの好きな人には堪らない本だと思うが、一般市民には若干ついて行けない部分がある。旧国鉄時代の駅名書体は楷書体筆文字が普通だったのが、1954年に丸ゴシック体(手書き)に統一、1960年「すみ丸ゴシック体(すみ丸角ゴシック体)」に変更された。まだ手書きで3社あり、東、西、九州で微妙に書体の差があった。現JR書体も基本形は受け継いでいる2024/08/30
ゐわむらなつき
8
今でこそワープロ書体が完成されているからどの駅に行っても統一された駅名標やサインがあるが、かつて手書きやカッティングに心血を注いだ先人たちあってこその賜だと感じた。表題には「されど」とある。多くの日本人はサインシステムやフォントに美を見出すことはないだろうが、何気なく利用している案内が整っていなければとりわけ東京の路線網は機能しなくなるだろう。鉄道関連の文字がこれほど重要だったとは、改めて気付かされる一冊。少し前にちらっと出てきた人が後々また大事なところで出てきて「誰だっけ」ってなることが多々…。2016/09/19
やまほら
7
鉄道で使われている文字の数々を紹介するだけの本かと思ったら、さにあらず。書体にこだわりを持つ須田寛JR東海相談役をはじめ、文字のデザイナー、琺瑯引き駅名票の業者、車体に直接文字を書く大宮の担当者、蒸気機関車のナンバープレートを作る業者等へのインタビューから構成されており、それぞれ今まで意識していなかったことに気付かされる、興味深い1冊だった。最後のロンドン地下鉄に関する部分は、説明不足で蛇足かな。あと、著者はかなり鉄道文字の写真を撮っているようだが、それがあまり活かされていないように感じた。2016/04/17
cipher
6
これは案内文字に関する鉄道知識の入門として、決定版と言えるのではないでしょうか。JR東海とすみ丸ゴシックの関係や、各種鉄道文字の系譜などが綿密な取材をもとに紹介されていてなかなかの読み応えでした。書体を文化と捉える風潮があれば、国鉄フォントも営団フォントも生き残ったのかなとふと思ったり。列車内の案内表記や、貨物列車等の職員向け案内など、文字に関する解説本が少ないのも、きっと書体とか認知心理への関心の低さからなんでしょうし2016/02/16