内容説明
援助という仕事の本質は「曖昧さ」「多様さ」にある。援助は、これらの本質を大切にして初めて技術や専門性を育てることができる。本書は、これらの援助の本質を踏まえ、援助が「創意工夫」の許される仕事であり、そこに「自在さ」という面白さが生まれる可能性を示唆する。
目次
第1章 援助における曖昧さ・無力感と「全能感幻想」
第2章 援助者の「自然体」について
第3章 援助と「大きなお世話」の相違について
第4章 理解と判断
第5章 共感と対等
第6章 質問と伝達の技術
第7章 グループと集団の相違について
第8章 グループの発達について
第9章 グループの発達とそれを促す技術
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みさきち
4
図書館。第4章・第5章・第6章のみ読了 今の自分にとって必要だなと思った箇所のみ読んだ2025/10/28
okaching
3
援助の面白さを明確に教えてくれる本。援助にとって自分自身との対話がいかに大事か再度理解させられる。自分自身の感情、熱意を踏まえ、支援をしていく。自分の弱さからつい自分の感情を無視してしまう。大いに反省が必要。2014/04/21
Red-sky
1
前半はケースワークについて、後半はグループワークについて。なかなかここまで言語化されている本もないのでありがたい。「意見を質問にすり替えない」は心当たりがあるかも…気をつけねば。内容は参考になるがところどころ時代も感じさせる。昔は相談者に電話住所教えてたってすごいな。2019/03/13
egg
0
職場の方からオススメのあった著者。自分では選ばないであろう本。職場で本を紹介し合えること、様々な職種の人が存在するという事実にまずは喜びを感じる。福祉、ケースワークについて精神論のみで論じられがちな内容を技術として取り出している。相手を理解し判断しようとする際に、自分に働きかけ、自分の状態を吟味する。このことばが非常に印象的。グループワークの章は、子育てや組織内のコミュニケーション、まちづくり分野やファシリテーションにも参考にできる部分があるのではないか。2013/11/30
r_tamapy
0
初めて、グループワークの意義が少しは理解できた気がする、今さらながら。。。2013/05/11
-

- 電子書籍
- 型技術 2025年9月号
-
![ギルト ~君の未来を奪う罪と罰~[ばら売り]第40話[黒蜜] 黒蜜](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1835502.jpg)
- 電子書籍
- ギルト ~君の未来を奪う罪と罰~[ばら…
-

- 電子書籍
- 離婚後夜【タテヨミ】シーズン2 022…
-
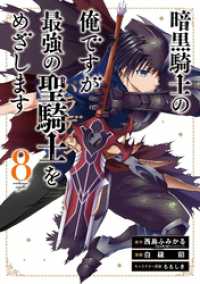
- 電子書籍
- 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざし…
-
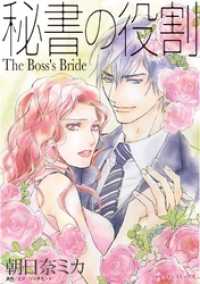
- 電子書籍
- 秘書の役割【分冊】 11巻 ハーレクイ…




