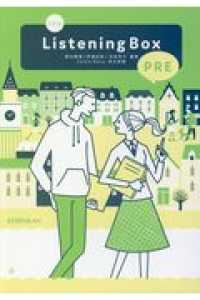出版社内容情報
動作療法へ行き着いた著者の70年に及ぶ足跡と動作療法の基礎から実際までを写真やイラスト入りで縦横に語り尽くした集大成である
本書は、70年に及ぶ催眠療法、精神分析、行動療法、サイコドラマ、自律訓練、イメージ療法、自己コントロール法等の研究の末に動作療法へ行き着いた著者の足跡と動作療法の基礎から実際までを写真やイラスト入りで縦横に語り尽くした集大成である。本書を読むと、心理療法がこころにはたらきかけるものではないこと、こころはからだに繋がっていて切り離せないことを理解できる。動作はこころを動かす、のである。
第?T部 動作療法
第1章 動作療法への階梯
1.心理療法一本の70年
2.催眠現象・催眠体験――意識・変性意識
3.催眠療法――イメージ・リハーサル、自分に適したやり方でよくなる
4.精神分析――内容よりも様式(仕方)
5.行動療法――過去よりも現在、行動療法にはこころがない
6.幻覚論――内容よりも様式、実感的体験
7.自律訓練――自己治療、実感的体験
8.イメージ療法――実感的体験
9.自己コントロール――自己治療、自己暗示、体験の実感化
10.脳性マヒ児者の動作訓練――こころとからだの一体化:生きるためには何よりもまず動くこと、動かす活動がこころを育てる
11.訓練キャンプで学んだこと
12.人間の動きの重点は肩周りと腰周り
13.おとなの肩凝りが治る
14.おとなの腰痛が治る
15.四十肩が治る
16.歩行困難が治る
17.全く新しい心理療法への曙光
第2章 動作療法の基礎
1.動作の成り立ち
2.動作のこころ
3.「努力」ということばについて
4.課題努力法
5.自己のこころ
6.動作・自己、両こころの調和と不調
7.自己暗示――自己暗示・他者暗示
8.体験
9.体験治療論
10.大地と重力
11.動作のこころの不調
12.こころの不調を確かめる――(何れも主動のこころから分離・解離)
13.こころからからだを解き放し・活かす
14.からだからこころを解き放し・活かす
15.真の自由は無意識化で
16.援助者(治療者)こころえ
第3章 動作面接の実際
1.クライエントの来訪――インテーク
2.動作療法の話し合い
3.動作面接過程への治療者心得
4.課題の動作を始める
5.動作療法は動作面接で進める
6.動作面接の役割
7.動作面接のプロセス
8.課題動作の進行に伴うこころの変化
第4章 動作体験の変化と生活
1.自動という動作
2.主動という動作
3.自己は動作を頼りに生きる
4.動作の課題努力法は意識化のプロセス
5.課題の努力過程で起きること
6.受け身(受動)・自動(能動)・やる気(主動)
7.症状形成の由来・メカニズム
8.“治す”と“治る”
9.動作療法で治る条件
10.自ら治し、治るために
第?U部 動作課題
第5章 動作療法は動作課題の達成努力が手段
1.動作を不調にしている背後の力
2.動作課題の作り方・用い方
第6章 基本課題
1.腰周り問題
2.肩周り問題
3.体軸問題
4.腕挙げ問題
5.頸・肩問題
6.腰周り動作の自由化
【著者紹介】
九州大学名誉教授、医学博士
内容説明
動作をこころとからだの一体化と位置づけた全く新しい心理療法。70年におよぶ動作療法の集大成。
目次
第1部 動作療法(動作療法への階梯;動作療法の基礎;動作療法の実際;動作療法での変化と生活)
第2部 動作課題(動作療法は動作課題の達成努力が手段;基本課題)
著者等紹介
成瀬悟策[ナルセゴサク]
1924年岐阜県に生まれる。1950年東京文理科大学卒業。東京教育大学助手等を経て、1969年~1988年九州大学教育学部教授。その間、九州大学評議員・教育学部長・心理教育相談室長等を併任。学外では、日本催眠医学心理学会理事長、日本心理臨床学会初代理事長、日本リハビリテイション学会初代理事長、日本学術会議会員等を歴任。退官後、九州女子大学教授・学長を経て、現在、九州大学名誉教授。医学博士。臨床心理士(第1号)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- いわて河童物語