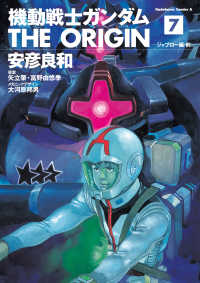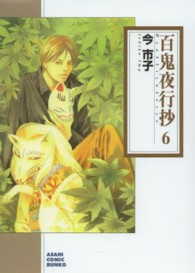- ホーム
- > 和書
- > 新書・選書
- > 教養
- > 青春新書インテリジェンス
内容説明
武将たちの興亡、古からの信仰心、渡来人の思い…山々に眠る歴史の封印がいま解かれる。
目次
第1章 戦略の山々―山に刻まれた「戦」と「武将たち」の痕跡(「妻坂峠」と畠山重忠の妻;万葉仮名の成立と漢字のいたずら ほか)
第2章 経済の山々―金・銀・鉄の山が見た興亡の歴史(安達太郎山とタタラの関係;全国に点在する「タタラ山」は何を意味するのか ほか)
第3章 宗教の山々―修験者たちが今に残したもの(山でもないのになぜ「成田山」か;日本人の信仰心を変えた大同年間 ほか)
第4章 外交の山々―渡来系文化、アイヌ文化が示す民族の交流(山をなぜ「ヤマ」「サン」「セン」と読み分けるのか;「ヤマ」は南方経由の痕跡 ほか)
第5章 山と日本人(日本人の御来光好き;「日出ずる国」に込めた思い ほか)
著者等紹介
谷有二[タニユウジ]
1939年愛媛県生まれ。日本山書会、産業考古学会、タタラ研究会などに所属。登山文化史研究家。日本全国のみならず、アジア各地で収集した多くの資料や情報を踏まえた上での歴史解読には定評がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
B.J.
11
●死者の霊は山に籠もるということで、平地にあるお寺にも山号をつけた。 ●アイヌ語には文字がないので、音に従ってどんな漢字を当ててもよい。「ポロ」には、大きいという意味があり、「ポロ・シリ」は、大きい山。「リ」は高いと言う意味なので、「リ・シリ」は、高い山。サッポロのサツは、乾燥した平野で、大平原となる。「ヌプリ」も山。紋別・芦別の「別」は、大きい川、真駒内・木古内の「内」は、小さい川。石狩川や沙流川ほどの大河になると、もう別も内もつかなくなってしまう。・・・本文より2020/02/22
ヴェルナーの日記
4
山名に関する視点から日本史を俯瞰していると著作者は述べているが、山の名前を突き詰めていくと、鉱山、そこから生れる山岳信仰、中国・朝鮮半島からの影響を深く受けているということであろうか。 日本史という歴史という視点ではなく、どちらかといえば、民俗学に類する書といえると思う。 その点で言えば、興味深かったが、惜しむなくは、いま少し深く掘り下げて欲しかったことと、日本各地の地形の説明するに略図なり地図等を示してほしかった。2012/06/05
パトリック
2
「山の名前」を読み解いているのは確かだが、「日本史」とくるのは違うだろうといいたくなる。古代史、中世史に関わる部分はあるが、どうみても「日本史」を語ってはいない。同じ名前の山をもう少し網羅的に示す方が良かった。ただ、真言密教とのからみで大同年間に開山された山が多いこと、のちに全国を歩き回った「高野聖」(実態は「売僧《まいす》」?)が信長や家康に弾圧されたことなど面白い指摘も多い。2019/06/11
たかむら
1
山の名前を読み解くと、鉱山などの金属(特に鉄)と権力者との関連が見えてくる…って、真新しい内容ではないなと言うのが正直な感想。教科書的な日本史からはあまり知られないが、少し日本史(特に古代史)に興味があれば知っているようなことが多い。一つ目・一本足の鬼の話など、それだけで一冊にできるのではないかと言うくらいだが、サラっと表面をなぞる程度。時々筆がスペるのか、横道にそれるのが逆に読みやすくてよかったりする。文字で色々と場所の説明がされているが、図表として地図を載せてくれればすぐ分かるのになぁと、少し残念。2013/08/27
yamakujira
1
山名の漢字表記にとらわれないで、山の名前に隠された歴史を推理する。著者の博学には感心するけれど、ちょっと強引なところもあるなぁ。 (★★☆☆☆)