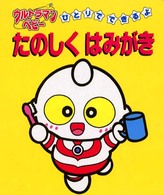内容説明
本を一生懸命読んでいるのに内容が理解できない人、頭に残らない人必見!「論理」で読めば、もっと速く、しかも確実に、要点をつかむことができるのだ。多くの受験生を合格に導いてきたカリスマ講師が、一生使える読書法を伝授する。
目次
第1章 頭がいい人は本の読み方が違う!
第2章 速読、多読を超える(出口式)読書法の秘密
第3章 ビジネス書の要点をすばやくつかむ!
第4章 文学書をもっと深く味わい尽くす
第5章 論文を書いて知識をアウトプットする
第6章 人生を変える読書の習慣
著者等紹介
出口汪[デグチヒロシ]
1955年生まれ。デジタル予備校SPS主宰、東進衛星予備校講師、出版社・水王舎を経営。関西学院大学文学部博士課程修了。在学中にアルバイトで予備校の教壇に立ち、独自の論理的解法を駆使した授業でたちまち人気講師となる。その後、能力開発のための画期的な日本語養成ツール『論理エンジン』を開発。現在、私立を中心に全国200校以上の小中高で導入されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
14
【1回め】ぼくはつくづく「読書論」が好きなんだなと思う。出口さんの本は、途中までのものを含めてこれが3冊目。この本の「売り」は、「頭をよくする読書法」ということだ。感性ではなく、「論理」立ててアプローチをして記憶し、それを「使う」ことが筋道であると説く。ただし、他の「多作」の方同様、「ようこそ、◯◯ワールドへ!」といった趣きがあることも否定はできない。基本的には、いまの読書のあり方を覆す必要はなさそうな感じである。2015/09/06
袖崎いたる
12
人間力は想像力である、といえるかもしれない。まず著者は画像・映像文化は「面白かった」とか「俺はあれ嫌いだわ」とかいった言明を誘発させる程度の、言語的吟味を通さない感覚的反応でしかないとし、想像力の強化には関与しないとする。だが活字文化は強化させうる。前者の言説は感覚文、後者は想像力=言語的認識を介した感想文といえ、読書の意義を説く。さて読書とは他人の思考の代理経験である。そこにおける想像力とは如何に個体としての断絶を超え、他者理解を行うかにある。これが難しい。その意味で解釈の多様性とは想像への甘えである。2015/08/19
anco
10
感情語を感性にまで高める。そのためには言葉を知らなければならない。論理の言葉は感情語のように肉体にはこもっていない。後天的に学習によって獲得するもの。読書によって言葉を操る力、思考力を鍛え、豊かな感性を身に付ける。読書から必要な情報を抜き取り、反復、記憶し、それを自在に使いこなせるよう、頭の中に回路を作る。2016/05/21
ポール
5
文章をある程度予測できる力 いかにいままで国語という教科をおろそかにしていたかがわかった。2016/04/22
ココアにんにく
4
本をたくさん読みたい。そう思って速読など試した時期がありました。今は読書で重視しているのは冊数より「どうしたら本から知識を身に付けることができるのか」です。いい本に巡り合いました。著者の浪人の話で驚き。本書を入手したのがこの大学のすぐ近く。紹介された本で未読の『沈黙』読んでみたい。目次の使い方、ためになる。目次を見て内容を予測するのが私の楽しみ。イコール関係、対立関係、A→B因果関係。実例を多く上げる外国のビジネス書など特にこの関係を意識するとずいぶん読みやすくなりそう。2019/09/16