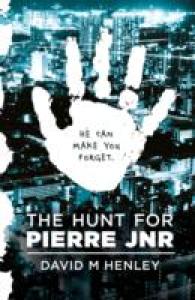出版社内容情報
古代の天皇信仰や神道思想など日本文化に深く刻まれた道教の軌跡を、仏教とも関連させつつ考察した画期的労作。新装版老・荘・易の三玄の学を基底におく中国宗教思想史の実証的な研究をふまえ、古代の天皇信仰や神道思想、陰陽道、医術薬学から明治の岡倉天心の宗教哲学にいたるまで、日本文化に深く刻まれた道教の軌跡を、仏教とも関連させつつ考察した画期的労作。
日本の古代史と中国の道教――天皇の思想と信仰を中心として
日本古代の神道と中国の宗教思想
八角古墳と八稜鏡――古代日本と八角形の宗教哲学
聖徳太子の冠位十二階――徳と仁・礼・信・義・智の序列について
山上憶良と病気――日本古代の道教医学
平安時代の道教学
風に乗る仙人
中江藤樹と神道
江戸期の老荘思想
益軒の『養生訓』と梅園の『養生訓』
三浦梅園と『荘子』と陶弘景
三浦梅園と道教
岡倉天心と道教
日本人と老荘思想
「木鶏」の哲学――名横綱双葉山によせて
『観音経』と道教――日本人の観音信仰によせて
京都と大陸の宗教文化
道教の研究と私――あとがきにかえて
福永 光司[フクナガミツジ]
著・文・その他
内容説明
老・荘・易の三玄の学を基底におく中国宗教思想史の実証的な研究をふまえ、古代の天皇信仰や神道思想、陰陽道、医術薬学から明治の岡倉天心の宗教哲学にいたるまで、日本文化に深く刻まれた道教の軌跡を、仏教とも関連させつつ考察した画期的労作。
目次
日本の古代史と中国の道教―天皇の思想と信仰を中心として
日本古代の神道と中国の宗教思想
八角古墳と八稜鏡―古代日本と八角形の宗教哲学
聖徳太子の冠位十二階―徳と仁・礼・信・義・智の序列について
山上憶良と病気―日本古代の道教医学
平安時代の道教学
風に乗る仙人
中江藤樹と神道
江戸期の老荘思想
益軒の『養生訓』と梅園の『養生訓』〔ほか〕
著者等紹介
福永光司[フクナガミツジ]
1918年大分県中津市生まれ。1942年京都帝国大学文学部哲学科卒業。同年10月熊本野砲兵聯隊入営。戦争末期に中国大陸に渡り、広東省で終戦を迎え、47年上海から復員。東方文化研究所(京都)助手、大阪府立北野高校教諭、愛知学芸大学助教授、京都大学人文科学研究所教授を歴任。1974‐79年京都大学文学部教授。1980‐82年京都大学人文科学研究所所長。定年退職のあと関西大学文学部教授、北九州大学外国語学部教授を勤める。その後、故郷の中津に住み、執筆・講演活動を行う。2001年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジャズクラ本
みのくま
水紗枝荒葉