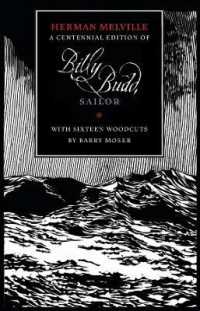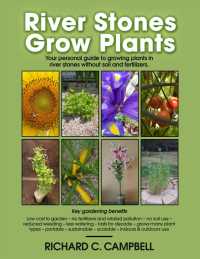内容説明
江戸時代の農村は本当に貧しかったのか。奈良田原村に残る片岡家文書、その中に近世農村の家計をきわめて詳細にしるした記録が存在する。本書ではその世界史的にも貴重なデータを初めて精緻に分析し公開。そこから導かれる数々の発見は、これまでの近世観を根底から覆し、世界水準の研究とも連携した歴史学の新たな出発ともなるだろう。なぜ日本人は貧困についてかくも冷淡で、自己責任をよしとするのか。日本史像の刷新を試み、現代の問題意識に貫かれた渾身の歴史学。
目次
第1部 世帯経営から見つめる貧困(村の「貧困」「貧農」と近世日本史研究;一九世紀初頭の村民世帯収支;家計から迫る貧困;生き抜く術と敗者復活の道)
第2部 貧困への向き合い方(せめぎ合う社会救済と自己責任;操作される難渋人、忌避される施行;公権力と生活保障;個の救済と制限主義)
著者等紹介
木下光生[キノシタミツオ]
1973年生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、奈良大学文学部准教授。博士(文学)。専門は近世日本史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イボンヌ
7
片岡家にのこる文書から貧困の実態を検証しております。湯浅誠さんや今野さんの本まで参考文献になっています。2019/04/06
デューク
5
21世紀日本は、生活困窮者の公的救済に冷たく、異常なまでに「自己責任」を追求する社会になっている。では、そのそも困窮者への支援はいかに始まり、今へとつながっているのだろうか。筆者の研究で明らかになったのは、元々村社会では村民相互の支援が主流で、公的支援は明治になって始まったものだということ。「『健康で文化的な最低限度の生活』を謳う憲法25条は、歴史的にみて画期的過ぎるため、その生活保障観念はいまだに根付いていない」との結言が、静かな衝撃として読む者の心を打つ一冊。いちおし2019/02/15
カモメ
4
税負担率は先進国最低水準でありながら痛税感が高く社会信頼度は最低の自己責任社会、日本。近世日本の生活保障は基本的に民間任せであり、領主御救は臨時的・限定的な性格を帯びていた。御救費が収支決算簿で「定式」ではなく「別口」という臨時費とされていた事からも読み取れる。また、働き方と素行で左右される制限主義や、村から米を施された際は厳しい制裁の対象とされた自己責任社会の特徴を持つ。これらは現在の生活保護受給の上での水際作戦にも繋がる。そして個の救済に関心が持たれるのは個別人身支配が志向される時代でもあった。2021/01/31
lovekorea
3
本編は学問的過ぎて、門外漢には難しいと感じましたが、序章の熱さに引き込まれて最後まで読めました。 『日本社会は、恒常的で十分な生活保障を良しとする歴史的訓練をまったく積み重ねてこなかったと想定される』 理由がとてもよく理解できました。 2019/02/01
京都の一読者
3
松沢裕作氏「書評 木下光生『貧困と自己責任の近世日本史』」、本書の読者には必読です。「本書がその問題設定に対し,歴史学的な史料分析に基づく研究として十分な寄与をなしえているかといえば,評者はこれに否定的である。(中略)総じて本書には先行研究の全面否定が目立つが,他者の研究に適用される厳しい基準が,著者自身の研究に適用されてはいないのではないか」。(『大原社会問題研究所雑誌』721、https://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/contents/721_06.pdf)2018/11/27