出版社内容情報
1945年4月7日、特攻に出た大和は沈没した。戦後も日本人のこころに生き続ける大和。大和の歴史は屈辱なのか日本人の誇りなのか。歴史のなかの戦艦大和をたどりながら戦後日本とあの戦争を問い直す。
~『戦艦大和ノ最期』から『宇宙戦艦ヤマト』『艦これ』までの15講!
【著者紹介】
1971年福岡県生まれ。九州大学大学院比較社会文化研究科博士課程中途退学。専門は、日本近現代史。博士(比較社会文化)。現在埼玉大学教養学部准教授。著書に、『近代日本の徴兵制と社会』(吉川弘文館、2004)、『銃後の社会史』(吉川弘文館、2005)、『皇軍兵士の日常生活』(講談社現代新書、2009)、『米軍が恐れた「卑怯な日本軍」』(文藝春秋、2012)、『日本軍と日本兵 米国報告書は語る』(講談社現代新書、2014)など多数。
内容説明
1945年4月7日、特攻に出た大和は沈没した。戦後も日本人のこころに生き続ける大和。大和の歴史は屈辱なのか日本人の誇りなのか。歴史のなかの戦艦大和をたどりながら戦後日本とあの戦争を問い直す。『戦艦大和ノ最期』から『宇宙戦艦ヤマト』『艦これ』までの15講!
目次
第1部 近代日本はなぜ大和を作り、失ったか―大和から日本の近代史を知る(海軍とは何のためにあるのか、戦艦とは何か;近代日本の歩みのなかで海軍はどんな役割を果たしたのか;昭和日本はなぜ戦艦大和を必要としたのか;実際の対米戦争で大和はなぜ活躍できなかったのか;一九四五年、大和はどうして沈んでしまったのか)
第2部 大和はなぜ敗戦後の日本で人気が出たのか―日本人の欲望の反映としての大和(占領期、大和はどうして日本人の心に生きることになったのか;一九六〇年代、なぜ子どもたちは大和に熱狂し、飽きてしまったのか;一九七四年、なぜ宇宙戦艦ヤマトはイスカンダルを目指して飛び立ったのか;そのとき、なぜ青少年はヤマトに熱狂したのか;一九八〇年代、戦艦大和はなぜ繰り返し映像化されたのか)
第3部 現在の私たちにとって太平洋戦争とは何なのだろうか―大和から考える(一九九〇年代、なぜ戦艦大和は仮想戦記に蘇ってアメリカに勝ったのか;二〇一三年、『宇宙戦艦ヤマト2199』と『艦これ』はなぜ作られたのか;もう一方の日本海軍の雄・零戦はなぜ日本人に人気があるのか;まとめ―戦艦大和と太平洋戦争とは戦後日本人にとって何だったのか)
著者等紹介
一ノ瀬俊也[イチノセトシヤ]
1971年福岡県生まれ。九州大学大学院比較社会文化研究科博士課程中途退学。専門は、日本近現代史。博士(比較社会文化)。現在埼玉大学教養学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nnpusnsn1945
Toska
まると
kanaoka 58
風見草
-

- 電子書籍
- 隣の元カレくん 5 マーガレットコミッ…
-
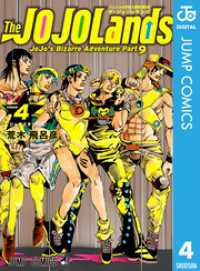
- 電子書籍
- ジョジョの奇妙な冒険 第9部 ザ・ジョ…







