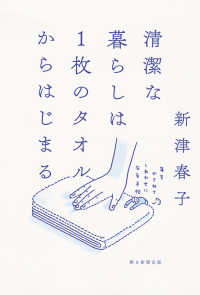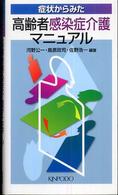内容説明
忘れられた東部戦線。言語や宗教の異なる諸民族が複雑に入り組む東中欧。いまだ国民国家を想像できない民衆の戦争経験とは。さらなる大戦後の帝国崩壊は、民族に何をもたらしたか。東中欧の「未完の戦争」の行方を追う。
目次
第1章 民族主義者の思惑(ポーランド問題;ウクライナ問題)
第2章 民衆の困惑(ポーランド人民衆の沈黙;ウクライナ人農民の悲劇)
第3章 ガリツィア・ユダヤ人の困難(民族のはざまに生きるユダヤ人;ユダヤ人の孤立)
第4章 隣人が敵国人となる日(一九一八年ルヴフ―ポーランド人とウクライナ人;ハプスブルク神話)
著者等紹介
野村真理[ノムラマリ]
1953年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程退学。現在、金沢大学経済学経営学系教授。一橋大学にて博士(社会学)。専攻は社会思想史・西洋史。著書に、『ウィーンのユダヤ人―19世紀末からホロコースト前夜まで』(御茶の水書房、1999、日本学士院賞受賞)、など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ののまる
14
海が国境で地勢的に他国と孤立し、ほとんどが単一民族単一文化で成り立っている日本では全く想像も理解もできない、民族や宗教・文化がモザイクのように入り乱れている東欧諸国。もとより「国家」「国民」「○○人」という概念もはぐくまれにくい。地勢的に大国ロシア・オーストリア・ドイツに挟まれ、政治的にも翻弄され続けた歴史。しかしそのどれにも迫害されるユダヤ人。バルカンやウクライナ問題など、今現在も同じ構造が繰り返されているが、その根本的原因が少しわかった。2016/05/24
Toska
10
ポーランド人とウクライナ人、ユダヤ人が入り混じるガリツィアの大地で、同じく複雑な民族構成を取るロシアとオーストリア・ハンガリーの両帝国が激突した第一次世界大戦。戦争がもたらす直接的な惨禍は言うまでもなく、戦後も失われた日常は元に戻らなかった。国民国家同士が真正面からぶつかり合った西部戦線に比べて注目度の低い、「忘れられた」東部戦線を描く。頁数は少ないが内容は重い。2024/01/22
えそら
6
第一次世界大戦期のガリツィア地方に混住していたポーランド人ウクライナ人ユダヤ人などの対立を概説した本。複雑に民族が入り組んだ地域で「国民国家」という新しい概念が、互いへの不満や疑念を紛争へ変えていく。一応は単一の民族で言語を持ちそれが「国家」だと信じて暮らす日本人にとって、学び取らなければ理解できない事なのではないかと改めて思った。貧しさに喘ぎながら暮すポーランドの農夫が、やはり貧しさに苦しむユダヤ人がそう仕向けていると信じ込む……こういった構図は現代にも通じるものだと感じた。2017/12/19
dongame6
6
「塹壕戦」「機関銃戦争」といった第一次世界大戦のイメージの多くを受け持っている西部戦線と比べ、「裏側」と思われがちな東部戦線ガリツィアで起きた、複雑な国境、民族、言語、支配と被支配の下で起きたウクライナ、ポーランド、そしてユダヤ人に関する諸問題とその結末。大戦前のガリツィアはどのような状態で、突如勃発した大戦の中で民族の大義を掲げる指導者達はどうふるまい、農民市民はどのような理由でそれぞれの指導者について行ったか。そしてそこで何が起きたか。民族自決とマイノリティについて考えさせられる一冊だった。2014/03/21
MUNEKAZ
5
第一次大戦期、オーストリア帝国統治下のガリツィア地方におけるポーランド人、ウクライナ人、そしてユダヤ人の民族運動をまとめた一冊。タイトルの通り同じハプスブルクの旗の下で生きてきた彼らが、少数の民族主義者と「国民」意識、そして周辺の強国に煽られて互いに敵となっていく姿が描かれている。被害者が加害者となり、相互不信が殺戮を呼ぶ様は衝撃的だが、この惨禍を生き残ってなお将来にはナチスドイツとスターリンのソ連が彼らを待っているわけで、地獄をのぞき込んだ気分になる。2017/08/29
-
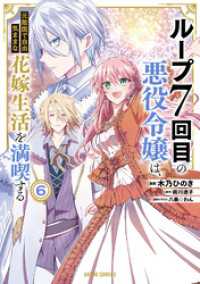
- 電子書籍
- ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由…
-
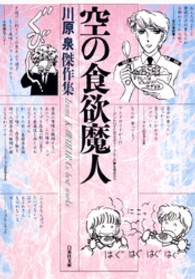
- 和書
- 空の食欲魔人 白泉社文庫