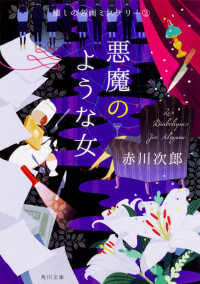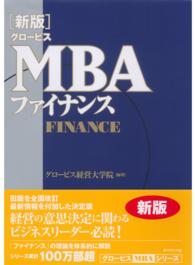- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
目次
第3部 黒色の年代(1968‐1971)(階級隊列の純潔化;上山下郷;戦争準備;大寨に学べ;更なる粛清;後継者の死)
第4部 灰色の年代(1971‐1976)(修復;静かなる革命;第二社会;反潮流;その後)
著者等紹介
ディケーター,フランク[ディケーター,フランク] [Dik¨otter,Frank]
香港大学人文学院講座教授。〓案館(党公文書館)資料を利用した研究の先駆者で、サミュエル・ジョンソン賞受賞作Mao’s Great Famine(2010)(『毛沢東の大飢饉』(2011年、草思社))、最新著書The Tragedy of Liberation(2013)をはじめとする10冊の著書は、歴史学者の中国に対する見方や認識を変えた。既婚、香港在住
谷川真一[タニガワシンイチ]
スタンフォード大学大学院社会学研究科博士課程修了(Ph.D.)。現在、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は現代中国の政治と社会、国際関係
今西康子[イマニシヤスコ]
神奈川県生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ののまる
11
よみきった! 文革後期に、農村から自発的に資本主義経済が発達したというのは、そうなんかな〜と思っていたら、やはり研究者からも疑問視されていた(あとがき)。でも林彪事件以降の雰囲気がよくわかった。2020/06/15
Hiroo Shimoda
10
毛沢東は強い猜疑心からNo.2が力をつけると叩き潰し、党や軍に対しても肩入れする先をコロコロ変えて争わせる。結果全体はボロボロ。この時代が中国人に与えた影響を想像せずに付き合うべきではないのだろう。日本人的な信用信頼が通じないのも当然ではないか。2020/11/06
templecity
10
文化大革命では知識人・若者は都市から地方に送られた。農業をするにも穀物のみとし、野菜やその他特産物の畑は潰された。住むところも鉄鋼重点施策で薪を取るため木々は伐採されてしまったので家具も含めて不足の状態。周恩来がまともそうだったが、癌に侵されても毛沢東が治療を認めなかったので死去。民衆は悲しんだが毛沢東が死んだ債はだれも心からは悲しまなかったと言う。鄧小平が個人所有なども認め、人民公社は解体され、ようやく悪夢の時代は終わった。だが天安門事件もあり共産党一党独裁時代は今も続く。 2020/09/13
masabi
8
【概要】毛沢東の死去、鄧小平が権力を固める。下巻。【感想】大衆に学べとするスローガンが発布され学生が農村に下放される。同時に都市部の過剰人口を農村に戻そうとする。虚構の成功事例を範として農村の自給自足を促すが、体の良い国家の経費削減策だった。一連の政治的動乱で経済が混乱し都市部でも農村部でも物不足、食糧不足は深刻で餓死者が出る始末にもかかわらず、毛沢東の死後も文化大革命は成功した政策とされた。混乱で共産主義イデオロギーと毛沢東の威信は低下し、資本主義経済の再興はもはや否定できなくなった。2022/03/01
健
8
前半は相変らずの権力闘争とそれに伴う下放施策に翻弄される国民という図で「いい加減にしてくれ」という気分になった。林彪が亡くなった頃から、政治に対する倦怠、無関心が広がり、文化大革命に対する否定的な考えが水面下で広く行き渡り、共産主義のイデオロギー自体を破壊したことが描かれている。やはり自由な経済活動こそが一番大事なのだ。また、周恩来が癌であるにも関わらず、そのことを本人に隠して治療させなかった毛沢東には唖然とする。いまだにその肖像画が掲げられている国家ってどうなんだろう。兎に角、文革の雰囲気が良くわかった2021/06/16
-

- 和書
- 刑務所の王 文春文庫