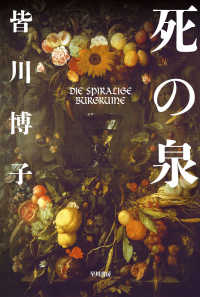目次
1 治療的面接学総論(すさんだ心の治療;面接における基本的心得―その質の向上のために;「自己学」としての精神療法;治療目的の相異に起因する面接特徴と患者体験からみた診断名の逆転性および治療的診断の必要性について ほか)
2 治療的面接学各論(一つの“病気”論の試み―医学教育における臨床心理学;催眠分析とイメージ―身・心イメージによる心の「整理」と「置いておくこと」について;メラニー・クラインの翻訳からの収穫―分析理論との擦り合わせから産出した持論の芽生え;Self helpとその内省をめぐる新しい精神療法の試み ほか)
著者等紹介
増井武士[マスイタケシ]
1945年和歌山市生まれ。1973年九州大学大学院教育学研究科博士課程修了。専門は精神療法学、治療面接学、メンタルヘルス論及びメンタルヘルスマネージメント。産業医科大学医学部助教授(教育学博士)、同大学病院精神・神経科および産業医実務研修センターを併任。日本心理臨床学会常任理事。同学会倫理委員長などを経て同学会編集委員、同学会理事などを歴任。2007年約30年にわたる産業医科大学退官後、東亜大学客員教授、日本産業カウンセリング学会理事などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
linker
1
本書の「自己学」という概念に出会っていなかったら、恐らく今でもこの仕事を続けていた…という自信はなかっただろう。仮に続けていたならば、嫌々やっていたか、何かの責任に追われてやらざろうえないかのどちらかであっただろう。どんな業種でも原理原則に縛られることが必ずといっていいほどあると私は思う。同様に、心理臨床の世界もそうである。しかしながら、縛りやルールの制約に飼われた人が相手の自由な気持ちの表現を促進できるハズがないのではないか…という発想を支持したのがこの「自己学」である。見落としがちな当たり前でもある。2016/05/15