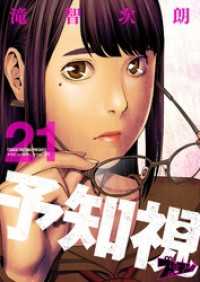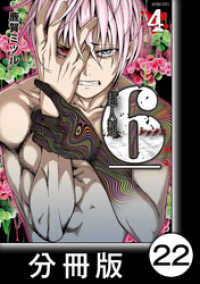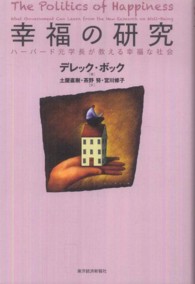出版社内容情報
博物館や美術館は、〈もの〉が展示されているだけの透明な空間ではない。それは社会に対してメッセージを発信し、同時に社会から読み解かれる、動的なメディアである。しかし、これまでミュージアムは主に展示する側の視点からしか語られてこなかった。本書では、メディア論の見地からその視点の転換を試みる。歴史的な検討を踏まえながら、ミュージアムをひとつの「思想」として考察する過程からみえてくるのは、日本と西洋におけるミュージアムの成りたちの宿命的な差異と、私たちのミュージアムに対する発想自体の貧困である。本書は“ミュージアムブーム”と“ミュージアム冬の時代”を同時に経験している現代日本にとって有益な示唆を与えるだろう。日本の新しいミュゼオロジーの展開を告げる画期作。
* * *
新しい時代の新しいミュージアムのあるべき姿と進む方向が本書によってようやく明示された。(青柳正規・文化庁長官)
ミュージアムはなぜメディアなのか。歴史と理論、実践を架橋する再定義で、運営論中心の陥穽から救う。これは、博物館・美術館の解体新書だ。(吉見俊哉・東京大学大学院教授)
【著者紹介】
東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学(博士、学際情報学)。京都精華大学人文学部専任講師を経て、現在、関西大学社会学部准教授。専門はメディア論、ミュージアム研究。共著書に、『マンガミュージアムへ行こう』(岩波ジュニア新書、2014年)、『ポピュラー文化ミュージアム 文化の収集・共有・消費』(ミネルヴァ書房、2012年)、『マンガとミュージアムが出会うとき』(臨川書店、2009年)がある。
内容説明
“ミュージアムブーム”と“ミュージアム冬の時代”は、なぜ同時に起きているのか?博物館・美術館大国ニッポンの未来を考える、画期的論考の誕生。
目次
プロローグ ミュージアムを異化するメディア実践
第1章 ミュージアムのメディア論―研究の枠組と方法
第2章 ミュージアム空間の思想
第3章 「ミュージアム」から「博物館」へ
第4章 メディア・象徴・メッセージ
第5章 二一世紀におけるミュージアム空間の変容
エピローグ 日本のミュージアムの今後と、周縁的であることの可能性
著者等紹介
村田麻里子[ムラタマリコ]
1974年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学(博士、学際情報学)。京都精華大学人文学部専任講師を経て、関西大学社会学部准教授。専門はメディア論、ミュージアム研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
tuppo
リョ
林克也
ぽん教授(非実在系)