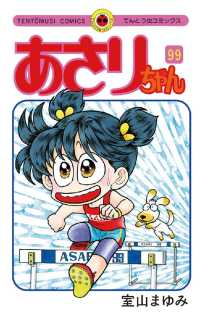内容説明
1980年代、アーサー・ダントーは「芸術の終焉」を唱えた。しかし、その後、現代アートはグローバル資本主義の拡大に同伴するかのように爆発的な隆盛を見せる。一方、芸術に向き合ってきた人文学はポストモダニズムの席巻の後、社会主義の崩壊、メディア技術の発展やアート自体の拡散も相俟って、理論的なものが後退してゆく。果たしていまや、この事態に斬り込む言葉はあるのか。本書では、「理論」を牽引するジャーナル『オクトーバー』『クリティカル・インクワイアリー』の変遷を軸に、現代思想とアートの複雑な絡み合いを読み解く。米国を越えて加速する世界規模の知のサーキュレーションを背景に、かつての理論的地平の乗り越えを試みる。
目次
1 理論(「芸術の終焉」以降のアートの語り方;ポストモダニズムとはどのようなものであったのか;ポストセオリーという視座)
2 批評(分断された肉体―寺山修司;ポストモダニズムを射抜く―ミックスド・メディア・シアター;紅のバラ―ピナ・バウシュ「窓拭き人」;イメージのマテリアリティ―アラン・セクーラ;イメージの制御、その行方―「渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの“映像演劇”」;呼び覚まされる声―三輪眞弘+前田真二郎「モノローグ・オペラ『新しい時代』」;黒いコードの群れ―クリスチャン・ボルタンスキー「Lifetime」)
3 討議 冷戦終結以降におけるアートと思想のサーキュレーション―ミハイル・ヤンポリスキーを手がかりに(+乗松亨平、番場俊)
著者等紹介
北野圭介[キタノケイスケ]
1963年生。ニューヨーク大学大学院映画研究科博士課程中途退学。ニューヨーク大学教員、新潟大学人文学部助教授を経て、立命館大学映像学部教授。映画・映像理論、メディア論。2012年9月から翌年3月まで、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kthyk
たろーたん
ozanarimakoto
す