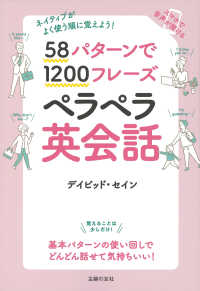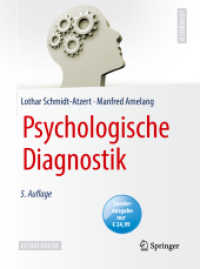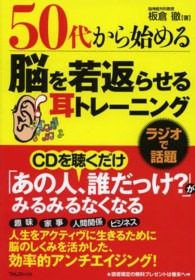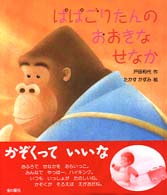内容説明
都市と映画館、アニメーション映画と初期映画、教育と映画、多言語映画とナショナル・シネマ等々、多次元的媒介作用のもとに見えてくる新しい映画史のスタイル。
目次
第1部 都市と映画の相関文化史(映画都市京都―映画館と観客の歴史;近代化する都市の映画観客―ニュース映画館の形態と機能)
第2部 初期映画とアニメーション映画(描く身体から描かれる身体へ―初期アニメーション映画研究;漫画映画の時代―トーキー移行期から大戦期における日本アニメーション)
第3部 ナショナル・シネマの諸相(アイヌ表象と時代劇映画―ナショナリズムとレイシズム;バベルの映画―スイスにおける多言語映画製作;戦火のユートピア―イーリング・コメディの系譜と現代イギリス映画の可能性)
第4部 教育と映画(映画教育運動成立史―年少観客の出現とその囲いこみ)
著者等紹介
加藤幹郎[カトウミキロウ]
1957年生まれ。映画批評家。映画学者。京都大学大学院人間環境学研究科教授。京都大学博士(人間環境学)。2002‐03年および1990‐92年、カリフォルニア大学ロサンジェルス校、カリフォルニア大学バークリー校、ニューヨーク大学、ハワイ大学マノア校フルブライト客員研究員。1999年、ミシガン大学客員教授。著書に『映画とは何か』(みすず書房、2001、第11回吉田秀和賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。