出版社内容情報
注目の思想家が挑む新しい社会実在論
組織や集合体から創造性はいかにして発生するのか
物質的/非物質的諸条件、ネットワークによる交流の反復を軸に、小さな共同体から、企業、都市、国家、社会運動までをフラットに分析。有機体的社会観の乗り越えと、偶然的な創発の解明に挑んだ、新しい社会実在論の試み。
*
デランダは、観念論でも実証主義でも捉えられないものとして、社会を思考しようと試みる。つまり社会を、人間の心の作用とは独立のものとして思考することである。観念や概念のふるまいや、システムや社会構造や言説といった知的構築物では捉えられないものとして社会存在を考える、ということである。デランダは、このような知の転換が要請される理由について、次のように述べる。「今や、人類が直面している問題の多くは、直接的には観察できない物質的な過程によって引き起こされています。それはすなわち、環境や河川や海の緩慢な汚染であり、大量生産において規格化された労働の拡散を要因とする、人間の技能の緩慢な低落です。」(訳者解説より)
はじめに
第一章 全体性に背反する集合体
ドゥルーズの集合体理論/集合体概念の二つの次元と四つの変数
反復的なものとマクロな集合体の発生/線形的な因果性について
因果、理由、動機
第二章 本質に背反する集合体
本質主義の回避/トポロジーとダイアグラム
マクロとミクロ、全体と部分/空間的規模と時間的規模
第三章 人とネットワーク
創発してくる主体のモデルとしての経験論/集合体としての会話
会議からの対人的ネットワークの創発/共同体の成立と社会運動
階級の実体と資源配分
第四章 組織と政府
組織の正当性と三つの型/空間、時間、言語による集合体の安定
集合体の資源依存の形、シリコンバレーとルート128
イノベーション、契約、カルテル/国家と行政
集合体の相互作用と正当性/集合体の同一性を強めるものと弱めるもの
第五章 都市と国家
建築の分析/土地の集積と分離/街と都市
中心地の階層秩序と海のネットワーク/都市と国家
市場と首都、言語、貿易/集合体理論の可能性
訳者解説
人名索引
【著者紹介】
マヌエル・デランダ/1952年、メキシコシティ生まれの哲学者、映像作家。1970年代よりニューヨークで活動する。主な著作に、A Thousand Years of Nonlinear History(1997)、Intensive Science and Virtual Philosophy(2002)、Philosophy & Simulation: The Emergence of Synthetic Reason(2011)など。翻訳に、『機械たちの戦争』(杉田敦訳、アスキー出版局、1997年)などがある。
内容説明
物質的/非物質的諸条件、ネットワークによる交流の反復を軸に、小さな共同体から、企業、都市、国家、社会運動までをフラットに分析。有機体的社会観の乗り越えと、偶然的な創発の解明に挑んだ、新しい社会実在論の試み。
目次
第1章 全体性に背反する集合体(ドゥルーズの集合体理論;集合体概念の二つの次元と四つの変数 ほか)
第2章 本質に背反する集合体(本質主義の回避;トポロジーとダイアグラム ほか)
第3章 人とネットワーク(創発してくる主体のモデルとしての経験論;集合体としての会話 ほか)
第4章 組織と政府(組織の正当性と三つの型;空間、時間、言語による集合体の安定 ほか)
第5章 都市と国家(建築の分析;土地の集積と分離 ほか)
著者等紹介
デランダ,マヌエル[デランダ,マヌエル] [DeLanda,Manuel]
1952年、メキシコシティ生まれの哲学者、映像作家。1970年代よりニューヨークで活動する
篠原雅武[シノハラマサタケ]
1975年、横浜市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。現在、大阪大学大学院国際公共政策研究科特任准教授。社会哲学、都市と空間の思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
渡邊利道
Mealla0v0
さのかずや
☆☆☆☆☆☆☆
-
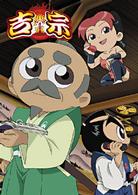
- DVD
- 吉宗 第三巻





