内容説明
丘の上は大邸宅、谷底は庶民の暮らし。100年前の地図を立体化!浮かび上がった台地と川の歴史を歩く。
目次
第1章 川を動かし海を陸地に(江戸時代)―銀座・日比谷・御茶ノ水・赤坂(御茶ノ水と神田川―都心部の今の地形は、江戸時代初めに改造されたもの;銀座・日比谷・丸ノ内周辺―皇居前広場や大手町、日比谷一帯は、入江の海銀座は半島だった 現在その痕跡がある!? ほか)
第2章 川を見下ろす権力の館―目白台・早稲田・水道橋・小石川(目白台と音羽の丘 神田川中流域―総理大臣の邸宅が連なる南向きの丘;早稲田・小石川界隈―池のある大邸宅群の存続と消滅。運命の分岐点とは)
第3章 複雑な谷が生んだ文化―麻布・六本木・高輪・白金(古川沿岸、港区周辺の台地概説―「古い地形」「無秩序に多い坂」に育まれた、山手特有の文化;麻布・六本木・飯倉界隈―「丘上の屋敷町」と「崖下の地」との断絶を散歩する ほか)
第4章 廃川跡 消えた川と取り残された川―渋谷・新宿・谷中・王子(明治神宮・竹下通り・渋谷川下流―さすがパワー水!?清正井の水が地下を流れだしたら、竹下通りが大発展;王子・滝野川・谷中―上流を奪われた藍染川、渓谷が生まれていった滝野川 ほか)
第5章 高い所に作られた川―玉川上水・三田上水(玉川上水―「奇跡のような西高東低の尾根」が可能にした江戸の上水道;三田上水・千川上水・青山上水―都心の台地に続く分水界を、うねうねと、みごとにたどった水路)
著者等紹介
内田宗治[ウチダムネハル]
フリーライター、編集者。1957年東京生まれ。早稲田大学卒業後、実業之日本社入社。旅行ガイドブック編集者、経済誌記者を経てフリーに。鉄道旅行ライター、地形(川と湧水)散歩ライター、地震防災ライターとして取材執筆の仕事が多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いくっち@読書リハビリ中
新平
yyrn
トモロー
takao
-
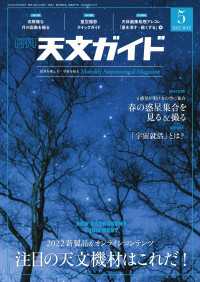
- 電子書籍
- 天文ガイド2022年5月号
-
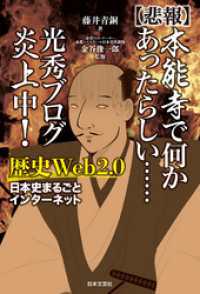
- 電子書籍
- 【悲報】本能寺で何かあったらしい…… …







