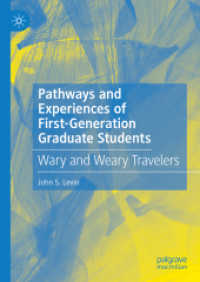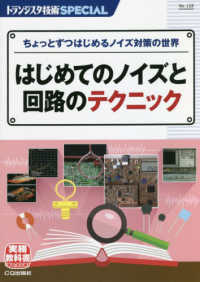内容説明
親を奪われた子ら、支援した人々の記録。
目次
第1章 駅の子たち(空き缶コップを持つ少年;戦争孤児とマッカーサー;いち早く開設された積慶園;報われない愛)
第2章 ある姉弟の歩み(ヒロシが平安養育院に入るまで;孤児対策として始まった「赤い羽根」;大人に反抗的だった姉)
第3章 伏見寮の人々(「赤いお屋根」;孤児を支えた指導員;大善院の遺骨と遺髪)
第4章 障害をかかえて(駅を転々とした全盲の戦争孤児;比叡山の麓に開かれた八瀬学園;二九歳で死んだ福井清子)
著者等紹介
本庄豊[ホンジョウユタカ]
1954年、群馬県松井田町(現安中市)生まれ。群馬県立前橋高等学校を経て、東京都立大学卒。京都府南部の公立中学校に勤務し社会科を教える。現在、立命館宇治中学校・高等学校教諭、立命館大学兼任講師、宇治城陽久御山地区労働組合協議会議長。専門研究は山本宣治を中心とする近代日本社会運動史、近代日本移民史、平和教育学。著書に長編推理小説『パウリスタの風』(群青社・紫式部市民文化賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
11
図書館本館新刊コーナーにて、この写真は!と思って手に取った。シリーズ戦災孤児で印象的だった写真だが、そのシリーズに関与していたとのことで納得。中身はダブる部分も多々。聞き取り調査の大半は孤児院関係者で当事者は男性2名(うち一人は盲目)とその姉(名前は仮名)の3名。1948年の全国孤児一斉調査のデータによれば京都の孤児は4608人。そのうち筆者が直接話を聞けたのはたったの3名ということになる。彼らの声は歴史に埋もれたままだ。2016/06/03
オリエ
0
「戦争孤児」を生み出すような国に2度とならないようにしなければと、強く思う。重い口を開いた体験者たち。「戦争の本当の姿を知ってほしい」と…。2016/09/07
海戸 波斗
0
浮浪児1945と併せて読みたい。戦争の悲惨さは残されたものにこそあることが分かる。東京大空襲で親を亡くした噺家の奥さんの裁判への行動が今ならわかる。みんなが耐えがたきを耐え、忍び難きを忍び。でってことですからじゃあんまりだ。でも広島への修学旅行で戦争体験者の話を聞くことのできなかった中学生を責めるのは間違ってると思う。真摯に向き合おう。どなたさまも一生懸命生きてるんだ。2016/03/31
〓
0
寡聞にして…なんだけど、「駅の子」上野駅の話かと思ったら京都駅の話でびっくりした。でも確かに大陸からは西日本の方が近い。日本における児童養護施設の多くは戦争孤児の収容所からスタートしてるらしい。先日里親してる方の記事を読んだこともあり、今も昔も皺寄せが子供に行くのがしんどい。トーヨコキッズとかネタにできることじゃない。終戦後の経済発展期の煌びやかな時代に自分の育ちのことが言えず病気を隠して亡くなった方の話とかあって、マズローのピラミッドは嘘な話とか(貧困の講義より)思い出しながら、世間と内面のギャップも2024/08/16
-

- 電子書籍
- 青蛇の赤い月【タテヨミ】第68話 pi…