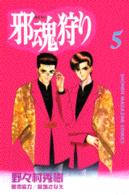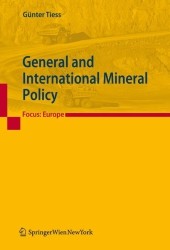内容説明
一九七〇年代から八〇年代にかけての定説であった部落差別の政治起源論では、部落差別にかかわる諸問題を解明することができなくなった。その諸問題を前にして、一九九〇年代に、部落差別発生を地域社会との関係の中で解明してゆこうとする試みや、中世の被差別民の実相を明らかにしてゆく方向性が打ちだされるなど、多様な研究が行われるようになる。本書では、諸問題解決のための、九〇年からのさまざまな「潮流」の具体的な研究を、著名な七名の著者の講演録をもとに収録する。
目次
日本中世における差別の諸相(網野善彦)
差別観念・ケガレ意識を考える(宮田登)
「身分」社会の理解(朝尾直弘)
権力は差別とどう関わるのか(秋定嘉和)
西京散所と北野社(細川涼一)
小法師論(辻本正教)
地域社会がつくる差別(薮田貫)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
浅香山三郎
14
奈良人権・部落解放研究所といふところの講演をまとめた本だが、内容的には中世〜近代に至る被差別民研究の諸潮流を知る上でもよいものだと思ふ。被差別民と天皇、東西の社会の違ひ(網野善彦)、共同体と差別観念(宮田登)などの問題をはじめ、社会の中の差別意識やその構造的再生産についてふれた論考が多い。秋定嘉和「権力は差別とどう関わるのか」は、とくに長くてむつかしいが、研究史整理が詳しく、近世〜近代の部落差別の構造理解を巡り、2つの潮流が党派的対立も含みつつ展開されてきたことがわかる。2021/02/20
牧神の午後
3
同和等に代表される差別について歴史上の起源を考察しているのだけど、ぶっちゃけ、ヒトのココロの中に差別があるということが思い知らされた。自分たちとは違う客人に対して特別な役割を持たせると同時に、その特別な役割故に、裏返しとして差別に繋がるところがあるのだろうか。2012/10/23
讃壽鐵朗
2
網野善彦以外は、難しすぎる2014/01/26