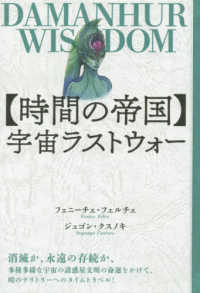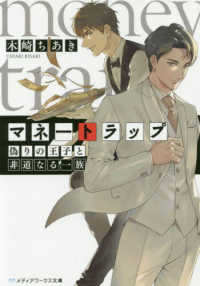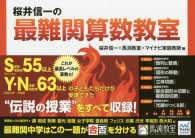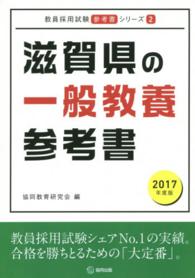内容説明
東大駒場は日本の大学の縮図。学者の人脈とその知られざる生態を浮き彫りにする。
目次
第1幕 四天王の誕生(芳賀幸四郎と芳賀徹;平川祐弘と東京高師附属中学特別科学組 ほか)
間泰曲 英文科の落ちこぼれ、比較へ行く(入院と院浪;大学五年生の生活 ほか)
第2幕 シンデレラ・ガールたち(華やかな年、一九八七年;三島憲一『ニーチェ』をめぐる小事件 ほか)
第3幕 神々の黄昏(修論と博論の関係はなかなか難しい;それほど芳賀と江藤の仲は悪いのかと思った ほか)
著者等紹介
小谷野敦[コヤノトン]
1962年、茨城県生まれ。本名読み・あつし。東京大学文学部英文学科卒、同大学院比較文学比較文化博士課程修了、学術博士。大阪大学言語文化部助教授、国際日本文化研究センター客員助教授などを経て文筆業。著書に『聖母のいない国』(河出文庫、サントリー学藝賞受賞)、など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
112
東京大学の教養学部における比較文学の人脈などをかなりマニアックな分析とゴシップで楽しませてくれています。他の本でもここに書かれている、駒場における四天王や御三家についての話を読んでいるのですが、この著者はかなり克明にその流れを追っている気がしました。どこの大学でもこのような派閥があるものなのでしょうね。2018/12/09
柳田
11
駒場学派の先生方は有名人が多くて、本もたくさん出ていて華やかな世界だ。し、やはり博識で能力のある方が多くいたところだということがわかる。ゴシップ満載で楽しい。帯に「日本の大学の縮図」と書いてあるけど絶対違う。東大比較文学比較文化研究室は、名前の通り文学研究が基本だが、哲学・思想をやっている人もいて、文学研究だからなのか、名のある方々だからなのかわからないが、伝記・評伝をたくさん書かれているのだなと思った。著者も大学は早々に辞められたが、谷崎、川端、里見、久米、大江に江藤と伝記をたくさん書いている。学統?2018/03/21
kenitirokikuti
7
図書館にて。再読。初読時にレビューなし。09年3月刊行で、あとがきにもあるように東京大学教養学部の非常勤講師の雇い止めと同時。直接の原因は禁煙に対する抗議。ひとところ「禁煙ファシズム」という声があがったが、実際のところ上からの大学組織改編による首切りの口実なんだろな、と思う。現在ではもう喫煙が話題になることはなく、女性差別か。小谷野せんせ、2003-06に国際日本文化研究センター客員教授だったが、同センターで連想するのはやはり呉座勇一か2023/01/05
kokada_jnet
6
ブログであらかたは読んでいたが、単行本で追加された「英文科の劣等性、比較へ行く」の章が白眉。文系の大学院の学生たちの「将来」がいかに教授たちに支配されているかが切実にわかる。そして、小谷野先生のその後の活動の原点はこの「大学院」時代にすでにあったような気がする。2009/05/14
透明ランナー
5
文学部学科間戦争とか中沢新一事件とかエリート観の変遷とか学制改革とか院浪とか右翼左翼、60年代から80年代の空気が伝わって意外と面白かったですり教わった教授の学生時代もちらほら2011/12/12