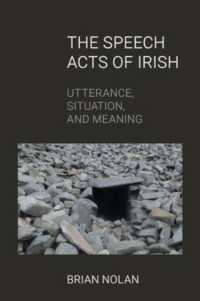内容説明
いつからこんなに忙しくなったの。
目次
第1章 時間革命(時間革命;近代史における「時間」)
第2章 時間の世界史(ガリヴァの懐中時計;シンデレラの時計を考える ほか)
第3章 時間の日本史(日本人の時間;シーボルトの旅 ほか)
第4章 アジアの時間(アジア・ルネサンス;アジア的価値秩序と近代世界システム ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ステビア
20
時間意識のポストモダン化/個人化=時間革命。色々なところに発表された文章を集めたものなので本としてのまとまりはあまりない2022/03/22
袖崎いたる
4
読み始めの頃はざっくり斜め読みでいいかなぁと思っていたのだけど、次第に目が離せなくなり、話題の広さと深さ、リサーチの堅さなどから読む目が鱗ぽろぽろと化していった一冊。時計の広がりから、時間意識の浸透、その浸透による文化の展開、さらには世界史の話に続き、本格的な文明論や西欧中心なる歴史観の批判をおこない、アジア文明の没落が西欧における工業・軍事的なる精神による「使命感という名のおせっかい的介入」によってもたらされたと述べる、このあたりの茶狂いと化したイギリスのありさまはなんともおもしろく、前のめりで読んだ。2025/04/23
のうみそしる
1
時間のパーソナル化黎明時代の書物。新聞の首相動静は昭和60年頃から分刻みで記載など、興味深い事実が多く書かれる。機械時計が生まれたことで、それまで日が出て沈んで寝ようかっていう生活が労働の基準として管理されるようになっていった。そしていまやデジタル世界。人々は息せき切って予定を埋めるのに勤しむ。そういう時間のとらえ方の話をもっと読みたかったが、後半はほぼ東洋と西洋の貿易の歴史、西洋中心史観の弾劾に取って代わられている。イギリス人が紅茶飲んで伝統とか言ってる時点で、最高級の皮肉なんだな。2025/07/15
アルゴス
1
西洋経済史を専門とする著者であるが、茶の歴史や時間の社会史などの著作もあり、幅広い視野が興味深い論点を提起する。シンデレラはどうやって夜中の十二時を知ったのか。問われてみると意外な問いであるが、当時の時計事情を知らされてみると、さまざまに思いが膨らむ。日本の明治の小説によくでてくる昼の「ドン」とは何だったかのか、世界でも珍しい日本の不定時時計である「和時計」とはどんなものだったか。話題作りにも最適なテーマが満載である。2017/11/17